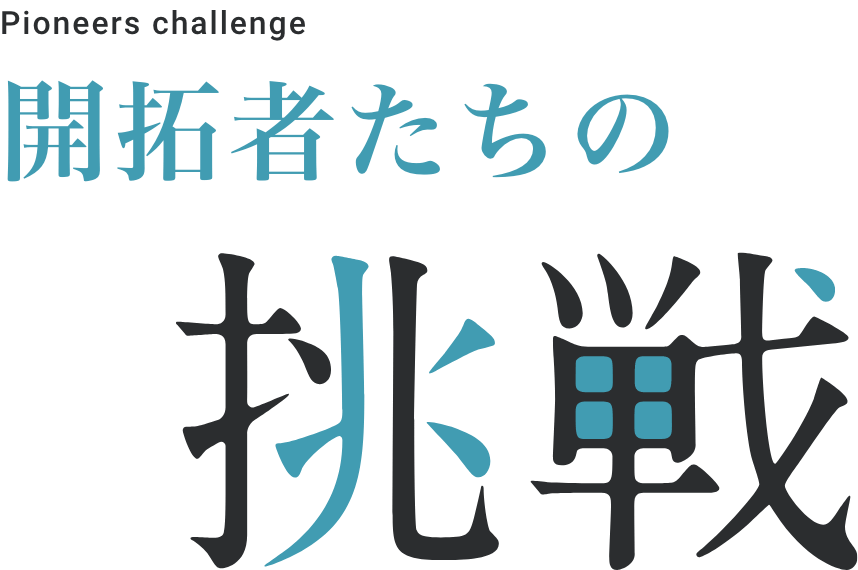

バイオサイエンス領域
植物生理学研究室
助教
久保田 茜 Kubota Akane
植物の巧妙でしたたかな開花戦略を読み解く
環境シグナルの統合点としての開花応答
花咲く植物は季節の移ろいを感知し、タイミングよく開花して種子を作り、次世代に子孫を引き継ぎます。植物は、自身の生存戦略のひとつとして、光や温度など周囲の環境要素の変動に応じて開花にふさわしい時期を予測し、調整する巧みなシステムを備えています。
動けない植物は定点観測するように、毎日の日照時間や気温の周期的な変化を継続してモニターします。例えば、葉で光を吸収して光合成をおこなう傍ら、感知した光情報と細胞内に存在する体内時計(概日時計)が刻む時間情報を統合することで、日照時間の長さを測り、自身が向かう季節を予測します。花器官を作り始めてから実際に種子ができるまでには様々な過程が存在します。植物は、光の他に温度などさまざまな環境シグナルを利用することで、自分を取り巻く季節や環境を正確に把握したうえで、結実までにかかる時間を逆算して、最適なタイミングで花芽形成をはじめるのです。
久保田助教はモデル植物のシロイヌナズナの季節に応じた開花適応の機構をめぐり、関連する遺伝子の活性化の解析など分子生物学の視点を導入して研究しています。これまでの研究で用いられていたように、光や温度を一定に保った単純条件ではなく、野外の自然環境を意識した環境を実験室で再構成することにより、さまざまな環境要素が関わる開花制御の実態を明らかにしています。
長日植物のシロイヌナズナは、日照時間が長くなるに伴い開花の準備をはじめます。そのとき、まず葉で花芽の形成を促進するタンパク質の「フロリゲン(花成ホルモン、FT)」を作ります。次いでフロリゲンは茎頂に運ばれて花芽づくりをスタートします。日の長さに応じたフロリゲン遺伝子FTの活性化機構は、陸上植物で共通してみられる仕組みですが、こうした仕組みが野外環境でも実験室と同じように機能しているかどうかはほとんど調べられておらず、世界中の研究者たちが「きっと野外も実験室と似たような現象が起こっているだろう」と想定していました。
そこで久保田助教らは「野外環境で生育した植物が、環境シグナルの刺激を受けて、どのようにFT遺伝子を活性化するかを詳しく調べたい」との発想で、シロイヌナズナを開花時期に相当する春先から初夏にかけて野外で生育させて、4時間おきに採取し、開花関連の遺伝子の働きを解析してデータを集めました。そして、主にFT遺伝子の働きを含む、開花応答を指標にして、実験室の環境を野外に近づける試行を繰り返しました。
その結果について、久保田助教は「これまでの開花応答の研究で用いられてきた条件ではFT遺伝子の活性化は日没時に1回のみ起こるとされており、世界中で日没時のFT遺伝子の働きが解析されてきました。しかし野外では、FT遺伝子の活性化は夜明けと日没の2回おこることがわかりました。夜明けの活性化には、長日条件に加えて、太陽光に含まれる遠赤外光が必須であることが分かりました。分子生物学の実験では、単純明快な実験設定が好まれますが、行き過ぎた単純化は生理応答の見落としにつながります。遠赤外光を多く含む白熱灯に代わり青色をはじめとする短波長側の光を多く含む蛍光灯が使われ始めた頃、一部の植物生理学者が、遠赤外光の効果を過小評価してしまうことを危惧していました。しかし、こうしたメッセージは蛍光灯の利便性により埋もれてしまいました。夜明けのFT遺伝子の活性化は正にこれに該当するケースだと思います」と説明します。

温度変動に応じた開花制御
久保田助教は、もう一つの重要な環境要素である「温度」についても研究を進めています。これまでの研究で、植物は1日の時間帯に応じて温度に対する応答性を変化させることで、夜明けと日没時のFT遺伝子の活性化を微調整し、開花時期を変化させていることなどを突き止めています。
同じ場所にいる限り毎年ほぼ正確に繰り返される、日長のような環境シグナルと異なり、温度は、1年あるいは1日の周期性をもった変化に加え、天候変化に伴う突発的な変化も起こります。「肌寒い夏の日」や「冬の間の小春日和」などニュースでよく耳にしますが、温度は日長と比較するとノイズ(乱れ)を含んだ季節シグナルです。それだけに「植物は体内時計を利用して1日の温度応答を変化させることで、季節認識に重要な平均気温を読み解いたり、日々移ろいゆく気温に追随して開花応答を変化させることができます。植物が日々の温度変動に対して発揮する、巧妙なデコーディングシステムを明らかにしたい」と話します。戦略的創造研究推進事業「さきがけ」に採択された研究テーマでは、日々の温度変動が開花応答を可塑的に変化させる仕組みや生物学的意味について、分子生物学の視点から解明します。
久保田助教は「今後も植物の開花応答をはじめ、環境応答全般にテーマを広げて、野外で生育する植物のいきざまを理解したいと思っています。いつか、分子生物学と生態学の橋渡しができるような研究分野を開拓していきたいです」と話します。
楽しくないと研究は続かない
久保田助教は、京都大学農学部に入学した当時は生物の基礎知識はほとんどありませんでした。しかし、友人に誘われて参加したゼミで水を通す膜タンパク質(アクアポリン)について学んだのをきっかけに、それまで全く知らなかった分子生物学や生化学に興味をもつようになりました。研究室配属では「動物実験が苦手」だけど「多細胞生物を扱いたい」との理由で、植物と遺伝子を対象にする「植物遺伝学」という研究室に配属を希望し、植物の生理応答の研究に従事するようになりました。
京都大学大学院生命科学研究科に進学し、長日植物のゼニゴケが、概日時計に基いて生殖器を形成する機構に関わる遺伝子について研究しました。その結果、シロイヌナズナの花成制御に関わる遺伝子と同じ仕組みを進化の過程で転用していることを突き止めました。
「学部4年生のときに、赤色や青色といった単色光の下で育てたゼニゴケが光の色によって大きく成長発達の様子を変える姿に衝撃を受けました。じっとしているように見える植物がダイナミックに成長を変化させる仕組みが知りたい、と思い研究をはじめました。あの時の新鮮な驚きが、いまでも私の研究の原点になっています」
その後、ワシントン大学生物学部の博士研究員として4年間過ごし、2018年に本学に赴任しました。
研究のモットーは、背景を理解して、楽しく研究を続けること。「研究は歴史だと思います。過去を理解し、未来につなげていけるような知見を残したいです。」と話します。
尊敬する人物は元メジャーリーガーのイチローで「調子のいい時も悪いときも一定のパフォーマンスを出すことを現役時代を通じて実践するプロフェッショナリズムを尊敬しています。出身が愛知県と同郷で、ワシントン大学は、シアトル・マリナーズの本拠地に近かったのですが、残念ながら一度もお目にかかったことはないです」と話します。趣味は地ビールの飲み比べ。美術館めぐりも好きで、印象派に加えて、最近出張のついでに訪れたベルギーの王立美術館で宗教画に触れ、感動されたそうです。





