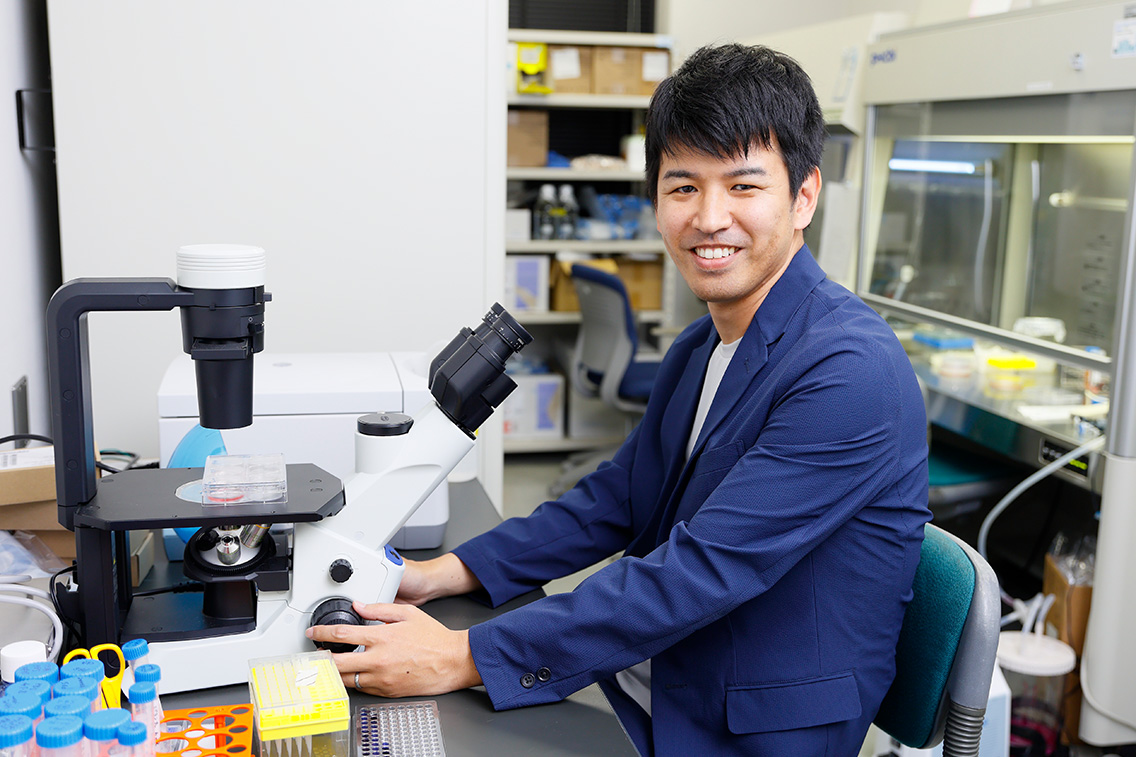

松田泰斗准教授が、文部科学大臣表彰 若手科学者賞を受賞
科学技術に関する研究開発で顕著な成果を挙げた研究者に贈られる「令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞」を本学バイオサイエンス領域脳神経機能再生学研究室の松田泰斗准教授が受賞しました。評価されたテーマは、マウスの脳内の損傷部位に集まる免疫担当細胞に対して転写因子を遺伝子導入し、機能が異なる神経細胞にリプログラミング(分化転換)させる研究です。脳梗塞を起こすマウスを使った実験では、この方法で新生した神経細胞は神経回路を組み、神経機能を回復することに世界で初めて成功しました。松田准教授は「これまでの十年にわたる研究成果が認められ嬉しく思い、多くの共同研究者の方に感謝しています。基礎研究の段階ですが、一日も早く臨床応用の研究に進めるよう努力していきたい」と話しています。
松田准教授は、脳梗塞などで損傷した脳神経の部位に、免疫担当細胞のミクログリアが集合し、機能を失った神経細胞を除去することに着目し、「このミクログリアを直接、神経細胞に改変させることはできないか」という大胆な発想を得て研究をスタートしました。このときは、奈良先端大の博士後期課程の学生で、バイオサイエンス研究科の中島欽一教授(現九州大学大学院医学研究院教授)の研究室に所属しており、着想のきっかけは、全くの偶然の出来事でした。研究室で、細胞の遺伝子発現をリプログラミングして神経細胞を得る方法に関する論文を読んでいたところ、「隣の席の学生が、脊髄損傷の部位にミクログリアが集合するという論文を調べていて、その図表をモニター画面で見た瞬間にひらめきました。当時の生命科学の常識では受け入れ難いアイデアでしたが」と振り返ります。
その後、中島教授の九州大学への異動とともに、同大に移って研究を重ねました。その結果、マウスでは、生体に脳が形成される過程で、神経細胞の産生に重要な働きをする「ニューロD1(ND1)」という1個の遺伝子をミクログリアに導入すると、ミクログリアにおいて、エピジェネティック(後天的な遺伝子発現の調節)な変化が起きて、その結果、本来は働きが抑えられているはずの神経細胞に分化する遺伝子が発現することで、神経細胞に変身することを突き止めました。さらに、この神経細胞は神経回路を形成して脳の機能の発揮に貢献することもわかりました。


表彰式での一枚。中島教授と揃っての受賞となりました。
再生医療では、細胞の遺伝子を一旦初期化して未分化のiPS細胞を作り、神経細胞を産生する研究が進んでいます。松田准教授の方法はマウスでの実験段階ですが、成体の細胞に転写因子を遺伝子導入して直接リプログラミングするので、大幅に時間やコストを縮小できる可能性があります。
松田准教授は「マウスの機能回復の実験は成功しましたが、ヒトでは複数の遺伝子が関わっていると見られます。しかし、再生医療には、絶対に必要な技術なので、手を尽くして解明したい」と話します。
また、加齢とともに脳機能が低下する現象のメカニズムについても研究を進めています。マウスを使った研究では、脳の機能低下に関わる遺伝子の働きを可逆的にエピジェネティックな制御をする主要な因子(Setd8)を特定しました。この因子の操作により、老化した神経幹細胞の「若返り」の可能性を示唆しています。
松田准教授は、九州大学大学院医学研究院講師から、2024年11月に本学に赴任しました。研究の心構えは「絶対無理とされるテーマをあえて選んで挑めば、その分野の先頭に立てる」です。「教科書を信じすぎない」ことも信条にしています。妻の松田花菜江(かなえ)さんも本学バイオサイエンス研究科の高山誠司教授の研究室の出身で、特任研究員として共に脳神経の研究に励んでいます。





