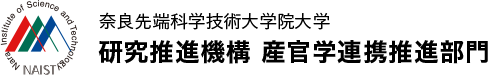- HOME
- 研究支援
- 研究支援情報
研究支援情報
外部資金獲得
研究推進部門では、様々な外部資金について、申請書作成支援、模擬面接・模擬ヒアリング等を行っています。
科学研究費助成事業
人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる「学術研究」(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」であり、ピアレビューによる審査を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。
URAが学内説明会、申請書作成支援を行っています。
JST戦略的創造研究推進事業
日本が直面する重要な課題の達成に向けた基礎研究を推進し、科学技術イノベーションを生み出す創造的な新技術を創出することを目的とした事業です。
URAが申請書作成支援と模擬面接を行っています。
JST創発的研究支援事業
特定の課題や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的イノベーションにつながるシーズの創出を目指す「創発的研究」を推進するため、既存の枠組みにとらわれない自由で挑戦的・融合的な多様な研究を支援する事業です。
URAが申請書作成支援を行います。今後模擬面接を行う予定です。
課題設定・プロジェクト型事業(内閣府、文部科学省、経済産業省、総務省、NEDOほか)
国等が定めた目標・設定課題を達成・解決するために、府省庁ならびに関連機関が大型事業・プロジェクトを企図し、実施者を公募しています。大学もまた、その英知を基に、研究成果を展開させることで課題解決に臨むことが期待されています。研究開発等の環境整備や拡充、研究成果の技術実証や社会実装、地域産官学連携開発の推進など、本学の研究開発の発展・拡大が期待される種々の事業への応募を推進・支援します。
URAは、説明会開催・情報収集・申請提案書作成や評価会対応の支援・その他フォローアップを行います。
国際連携
海外研究機関との国際的な連携強化を推進
国際的な共同研究を推進するためには、基盤となる連携の強化が重要です。研究推進部門では、本学と海外の大学等の研究機関との人的交流および研究交流を促進させ、ネットワークの構築、共同研究の推進、ひいては研究力の強化に貢献します。
本学の研究力強化促進のための国際共同研究の調査・分析
本学の研究者と海外の大学等の研究機関との新たな共同研究の展開についての調査・分析を行っています。また、新規に設置する海外拠点先の選定や、国際共同研究室に招へいする海外の研究機関についての調査を行っています。
海外拠点となる国際共同研究室を設置
海外研究拠点整備プロジェクトにおける設置先の研究機関との交渉・契約の締結を行います。また、研究室の活動を支援し、プロジェクトを推進しています。
海外から本学に著名な研究者を招へいし国際共同研究室を設置
国際共同研究室整備プロジェクトにおける招へい先の研究機関との交渉・契約の締結を行います。また、研究室の活動を支援し、プロジェクトを推進しています。
海外の研究機関との国際シンポジウムの企画・運営
国内外で海外の研究機関と国際シンポジウムを開催することにより、海外との共同研究を推進しています。
国際情報発信
研究成果等をオンラインニュースサービスやNAIST Research Highlightsで紹介し、本学の研究を海外に発信しています。
詳しくはこちら人材育成
若手研究者発掘・育成プロジェクト
研究大学強化促進事業における「若手研究者発掘・育成プロジェクト」として、5年後、10年後に世界を先導する研究領域の開拓を目指し、意欲的な研究を進める若手研究者を積極的に登用しています。自立した若手研究者を育成する「テニュア・トラック制度」により、将来本学の柱となって研究を担う若手研究人材を世界から公募・採用する体制を整えており、国内だけでなく外国人研究者も視野に入れて国際競争力の強化を図ります。
本システムは先駆的な研究分野を創出するために、意欲的な研究を進めている若手研究者に、テニュア・トラック准教授として独立した研究者の地位と研究環境を付与し、5年後のテニュア審査を経て、大学の将来を担うリーダーである教授として登用するという点で、他学に類を見ないシステムです。
このプロジェクトにて設置するテニュア・トラック研究室は、研究推進部門研究推進部の新プロジェクト研究室内にて運用されますが、将来の受け入れ予定領域にも兼務で所属し、学生の受け入れなど、研究科運営にも関わります。
戦略的研究チーム強化プロジェクト
「戦略的研究チーム強化プロジェクト」では、世界をリードできる研究チームを戦略的に育成するために、重点支援を行っています。
特に優れた研究業績を上げつつあり、本学が特に飛躍的に伸ばしたいと評価した研究チームに、博士研究員もしくは特任助教を研究スタッフとして重点配置し、若手人材の育成を図るとともに、研究チームが我が国のトップ研究グループに発展するよう、将来に向けた研究力の発展を図ります。現在は情報科学、バイオサイエンス、物質創成科学の3領域それぞれについてチームを選定し、研究スタッフを配置しています。
現在支援中の研究室
- バイオサイエンス領域
- 発生医科学研究室
- 物質創成科学領域
- 量子物理工学研究室
異分野融合
次世代融合領域研究推進プロジェクト
本学の第2期中期目標のうち大学の基本的な目標として、『基盤的かつ社会との関わりの深い学問領域「情報科学」、「バイオサイエンス」、及び「物質創成科学」の深化、拡大』が掲げられています。次世代を先取りする学際・融合領域を新たに開拓し、世界をリードする研究活動を積極的に展開するために、2010年度より、研究科の枠を越えた教員のブレインストーミングに基づく研究提案を選抜し、「次世代融合領域研究推進プロジェクト」として推進しています。
若手研究者ネットワーク開拓ワークショップ
本学研究者が、国内外の若手研究者との新たなネットワークを築きながら、リーダーシップを発揮するための活動を支援することを目的として、2010年度より「奈良先端未来開拓コロキウム」事業を開始いたしました。さらに、本事業をベースに、新たな研究領域の開拓や各研究分野の深化に重点を置く「異分野融合ワークショップ」を2015年度から開始しました。2021年度より、異分野の研究者との交流に限定せず、イノベーションの創出に資する最先端研究に関する研究者との交流を目的として「若手研究者ネットワーク開拓ワークショップ」を開始しています。
地域産官学金連携開発の推進
世界レベルの研究開発はもはや単独では困難となり、地域産官学金の協働による科学技術・イノベーションの発展が望まれています。近畿圏基本整備計画による関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)整備など、近畿圏は、大学等を中心に蓄積された研究成果の展開が期待されています。持続的なイノベーションの創出を目指し、リサーチコンプレックスの定着や新たな連携・協同開発の推進、新事業・起業の支援、地域の公的機関との協働などにより、地域経済の発展に向けたエコシステム形成を推進しています。