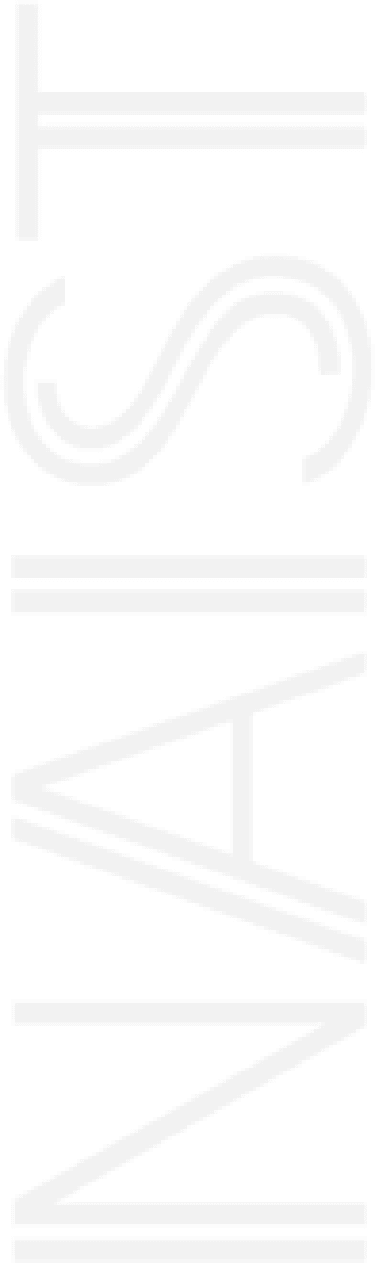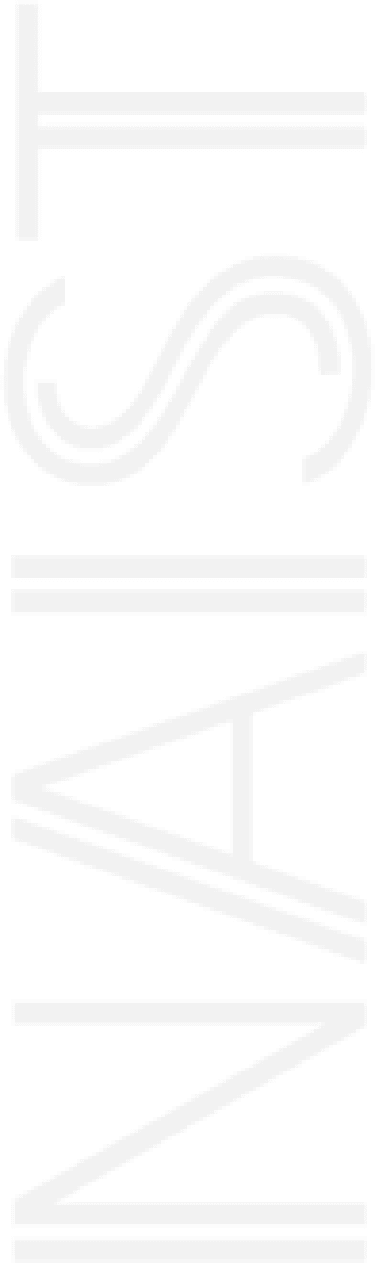スタートアップ創出で
研究成果を社会に
役立てる道を拓く
加藤 博一 理事・副学長
✕
澤邊 太志 准教授情報科学領域
インタラクティブメディア設計学研究室
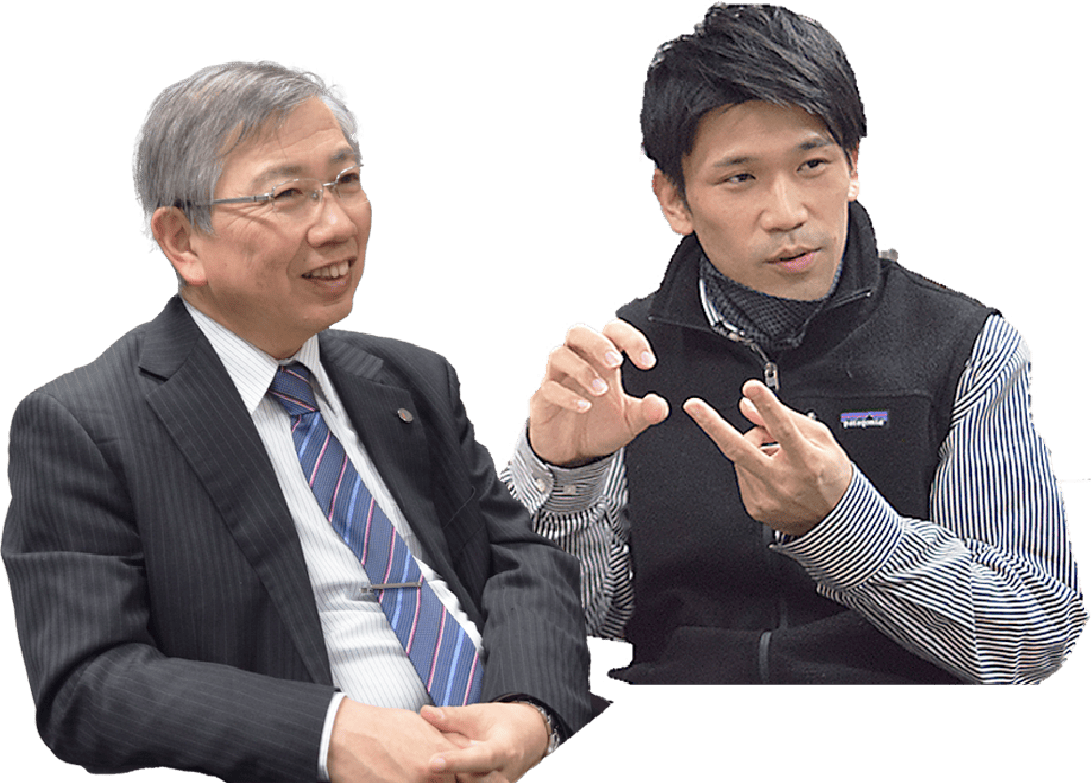
スタートアップ創出で
研究成果を社会に役立てる道を拓く
加藤 博一 理事・副学長
✕
澤邊 太志 准教授情報科学領域
インタラクティブメディア設計学研究室

大学の優れた研究成果をもとに、研究者自らが起業する
大学発スタートアップ創出の機運が盛り上がっています。
奈良先端科学技術大学院大学は、早くから、アントレプレナーシップ(起業家精神)を持った
人材育成をめざすプログラムを開講しており、すでに大学発ベンチャーが育っています。
そこで、加藤 博一 理事・副学長(兼・情報科学領域インタラクティブメディア設計学研究室教授)と、
スマホのアプリ開発の大学発ベンチャー「amirobo tech」の経営と本学教員を兼業している
澤邊 太志 准教授(情報科学領域インタラクティブメディア設計学研究室)が、
教員による大学発スタートアップの現状、あり方について対談しました。
profile
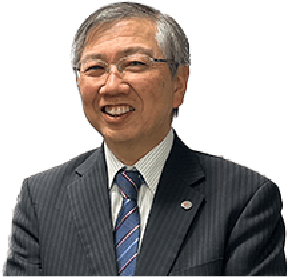
加藤 博一 理事・副学長
経歴
-
1988
3月
大阪大学大学院基礎工学研究科前期課程修了
工学修士 -
1989
4月
大阪大学基礎工学部 助手
-
1996
1月
博士(工学)
-
4月
大阪大学大学院基礎工学部 講師
-
1999
4月
広島市立大学情報科学部 助教授
-
2003
4月
大阪大学大学院基礎工学研究科 助教授
-
2007
4月
本学情報科学研究科 教授
-
2010
4月
本学 学長補佐
-
2013
4月
本学情報科学研究科 副研究科長
-
2017
4月
本学総合情報基盤 センター長/附属図書館長
-
2018
4月
本学先端科学技術研究科情報科学領域 教授
-
2021
4月
本学デジタルグリーンイノベーションセンター 教授
本学 学長補佐 -
2023
4月
本学 理事・副学長(〜現在)

澤邊 太志 准教授
経歴
-
2016
3月
本学情報科学研究科博士前期修了
修士(工学) -
2019
3月
本学情報科学研究科博士後期課程修了
博士(工学) -
4月
本学先端科学技術研究科情報科学領域
博士研究員 -
2021
4月
本学先端科学技術研究科情報科学領域 助教
-
2024
11月
本学先端科学技術研究科情報科学領域 准教授
趣味
映画、ドラマ、アニメ鑑賞、LEGO、写真
休日は、映画鑑賞や猫と遊び、非日常的な世界を楽しむことで、リラックスしています。
interview
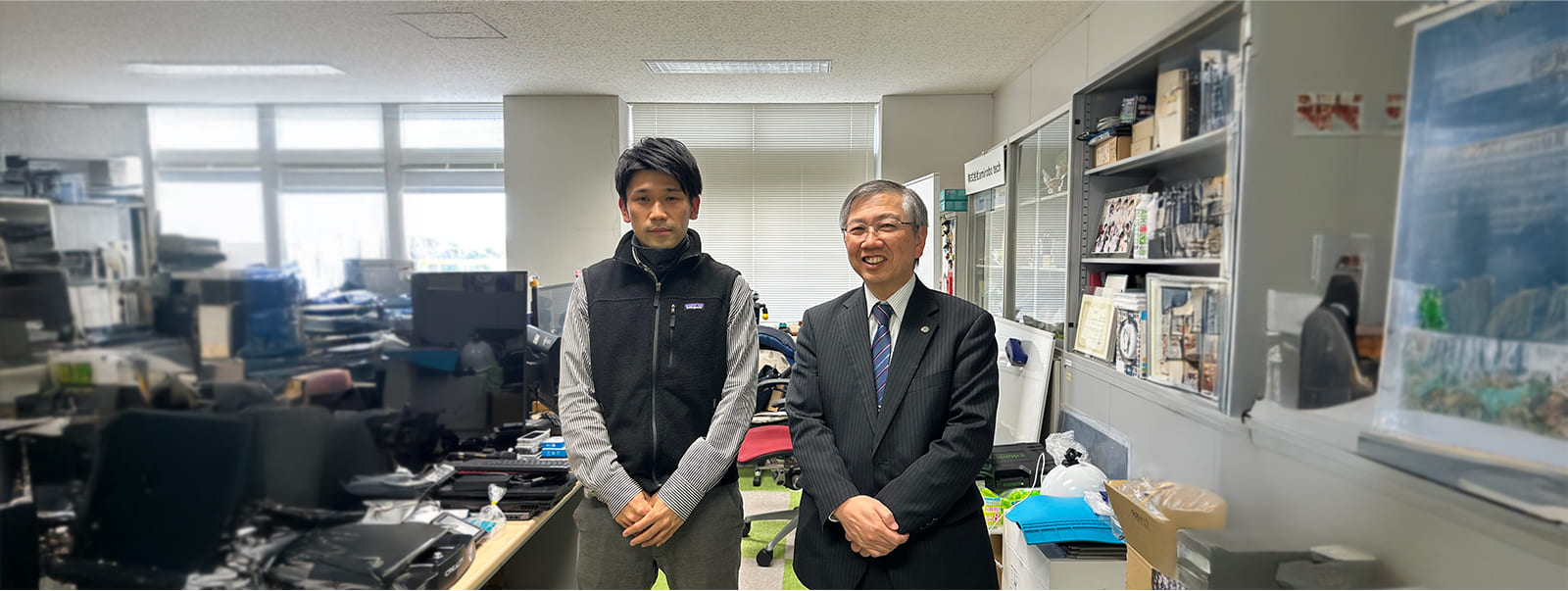
起業家精神教育を10年前から実施

加藤理事・副学長
本学がアントレプレナー(起業家)やイノベーション(技術革新)を目指す人材育成プログラム「Global Entrepreneurs on Internet of Things (GEIOT)プログラム」をスタートしたのは2015年でした。当時の日本は、米国に比べて大学発ベンチャーなどの立ち上げが遅れており、文部科学省が起業意欲を高める教育を推進するための補助金を得てスタートしたのです。
平日は学生が研究に集中できるように、また学外者が来場しやすいように、毎週土曜日に大阪市内で開講しました。多くの大学が産学連携部門で起業家教育を担当するのに対し、本学では私たち情報科学分野の教員が中心になって、主に情報科学領域の学生に対して講義し、ベンチャービジネスの経営者らを招いて、ビジネスプランについて教育しました。当時は学内に起業という考え方も浸透していない時代で、教える側も手探りでした。
現在は、バイオサイエンス領域や物質創成科学領域の学生も受講しており、2024年度は開始当時(30人)の倍の応募があるほどの盛況です。

澤邊准教授
本学情報科学研究科(当時)博士前期課程2年生のとき、GEIOTの初年度から参加しているゼロ期生です。理工学部に在籍していた学部生時代、経営学部の起業家教育の科目を受講しましたが、新たな科学技術をビジネス展開する内容の講義はほとんどありませんでした。本学に入学し、研究を続けるとともに、そのシーズをビジネス化、社会実装する方法を学べると思ったのが、GEIOTに参加したきっかけです。
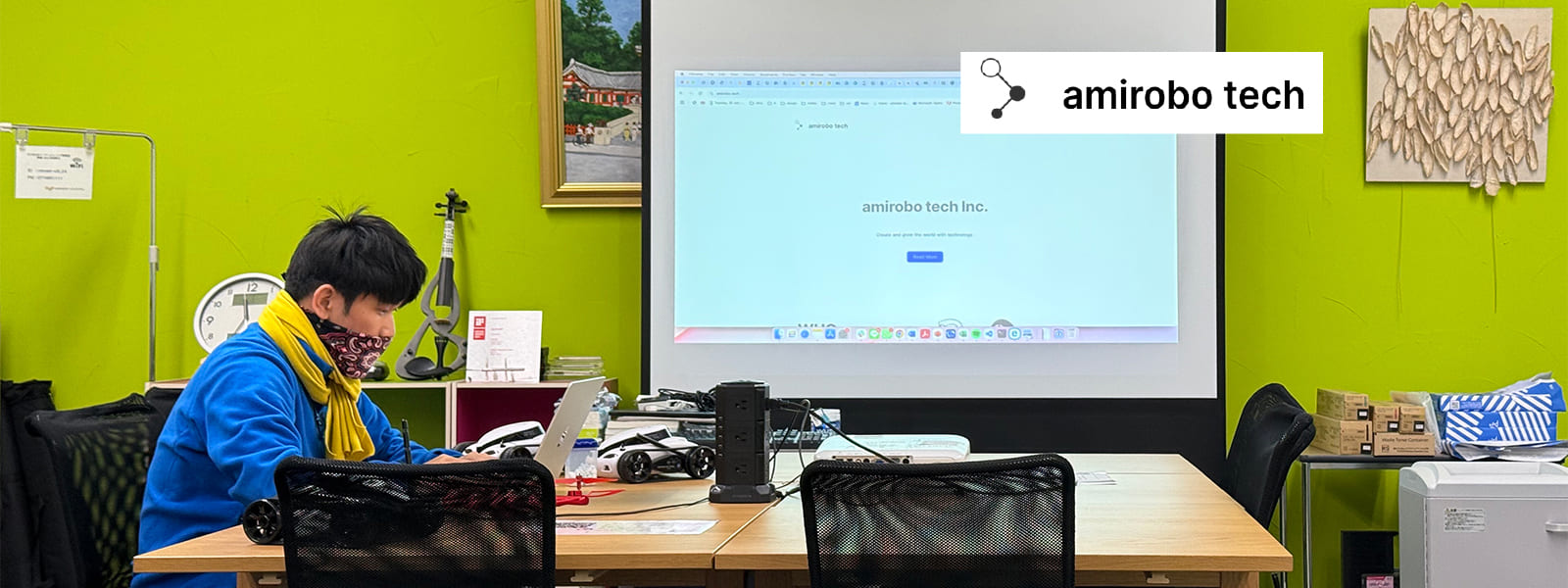
ビジネス化の課題がみつかった

加藤理事・副学長
スタートアップは研究して論文を書くことがゴールではなくて、その先の研究成果を使ってどのように社会実装するか、ビジネス化して利益を得るかというところがもう一つのポイントです。そこまで見通す能力をつけるのが起業家教育でしょう。確かに研究者にとっては、自分が開発に関わった技術の成果が街中で見られると嬉しいものです。誤解されやすいのですが、すべての研究者が起業しなければならないということではなく、基礎研究に取り組む研究者、企業との共同研究に力を入れる研究者、スタートアップする研究者のように、多様な研究者が大学の研究を進めるのが理想ですね。

澤邊准教授
GEIOTで学んだ後、博士後期課程の時に、amirobo techを起業しました。元々は学生として高齢者の見守りをする人型対話ロボットを設置して、その効果を調べる研究をしていましたが、ロボットは高価なため、現実的な課題解決の観点でネックでした。そこで同時に開発していたキャラクターが対話するスマホのアプリを使って調べることにしましたが、実験では被験者の属性に偏りがあり、人数も限られるという問題があるため、アプリを一般公開して対話のデータを収集し、実際に見守りができているかを検討することにしました。その段階で、アプリをリリースするための会社を作りました。ただ、今後のビジネスに改善すべき課題は、研究段階で想定していたユーザーと実際にお金を払って使ってもらえるユーザーとの間にギャップがあり、修正が必要なこと。もう一つは著作権の使用料などコストに反映する法的な知識です。いずれも技術研究だけではわかりません。
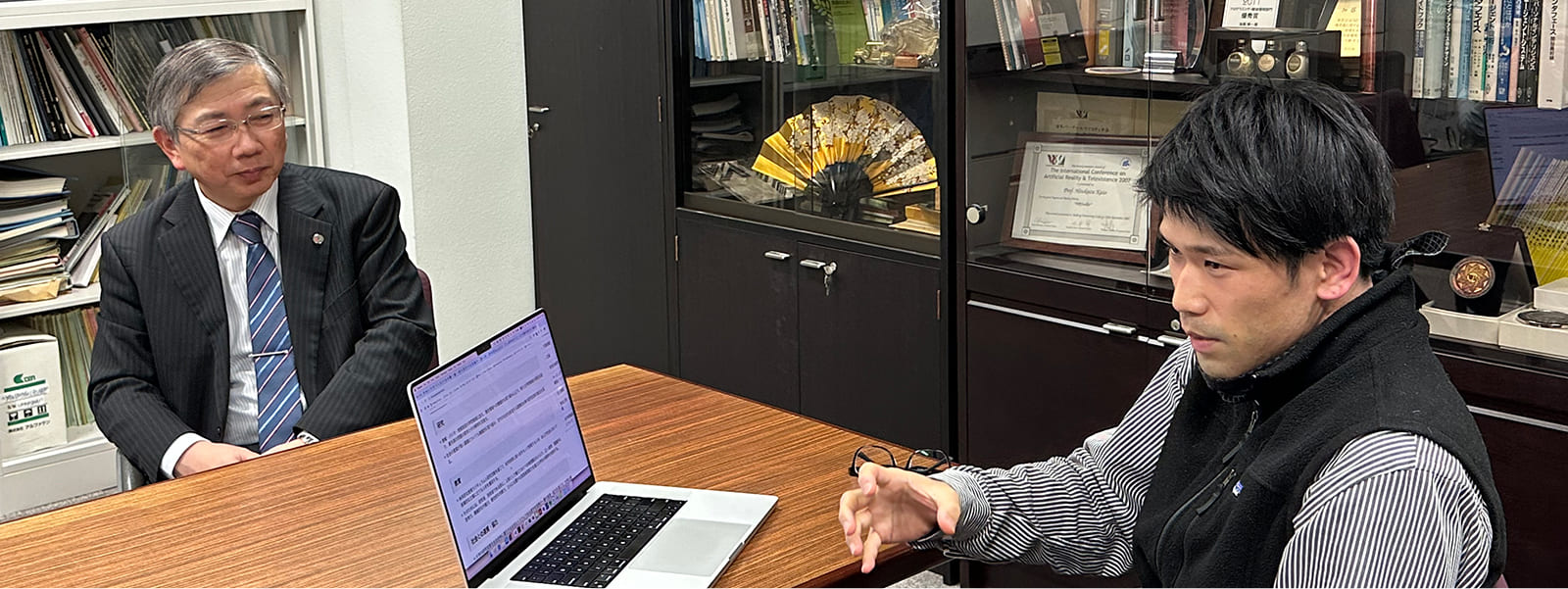
研究活動と両立するか

加藤理事・副学長
大学発スタートアップの経営には、様々な形態があり、澤邊先生の場合は、研究者が自ら社長になり、経営にも関与しますが、それとは別に、大学の研究者は、技術だけを提供して、会社経営は外部の専門家に任せるというやり方もあります。後者の方が本学にとっては成功しやすい方法と思います。ただ、研究成果を十分に理解し、研究のペースに合わせて情熱を持って取り組んでくれる人材を探し当てるのは非常に困難です。澤邊先生は、あえて、研究と社長業の兼業を楽しんで取り組んでいますね。

澤邊准教授
そうですね。一人で研究室運営をすると大変ですが、インタラクティブメディア設計学研究室は、教員や学生でチームを組み、役割分担して運営しているので、兼業に取り組みやすいです。※本学は大学院大学なので研究環境が整っていますし、近隣のけいはんな地区の企業との交流を通じてビジネス視点のコメントが得られます。学生も他大学出身者や高等専門学校出身者、留学生など多様で、それぞれの技術研究の強みが実応用のヒントになることもあります。大学としてスタートアップをする障壁が高くないのもよいと思います。
スタートアップは、小規模の資金で始めるスモールビジネスですが、社会課題を解決するという重要な目標を持って事業展開し、世界規模にも成長していけるところが、研究者としてやりがいを感じています。ただ、研究論文は学術的に評価されても、その技術の経済的な影響が一般ユーザーにどこまで及ぶかということについては、経営の専門家の推測や助言が必要かもしれません。また、起業時期で会計年度の始期と終期が決まるのですが、私は冬季に起業してしまったために、毎年amirobo techの決算が修士論文の審査の時期と重なることになり、時間管理と作業が大変です。これは誤算でした。
※事務局注:役員兼業にあたっては事前に許可申請が必要です。ご検討の場合、人事課までご連絡願います。

さまざまな分野でのビジネスを

加藤理事・副学長
科学技術振興機構大学発新産業創出基金事業の支援を受け、関西スタートアップアカデミア・コアリション(KSAC)が関西の大学の研究開発課題を対象に資金提供を行う「KSAC-GAPファンド」において、2024年度に採択された本学の課題は、情報科学領域2件、バイオサイエンス領域1件、物質創成科学領域1件の計4件で、このうち2件が健康管理、発酵食品といったヘルスケア分野の研究です。ヘルスケア分野のスタートアップが多いのは、全国的な傾向です。また、大学発スタートアップとしては、物質創成科学領域の研究と深い関係があるディープテックが大きな注目を集めています。本学でも、スタートアップにつながる有望な研究シーズを発掘する部門を充実させる必要があるのではないでしょうか。若手教員には本学の理念・目的を意識して、研究成果のその先に大きな夢を見てほしいですね。