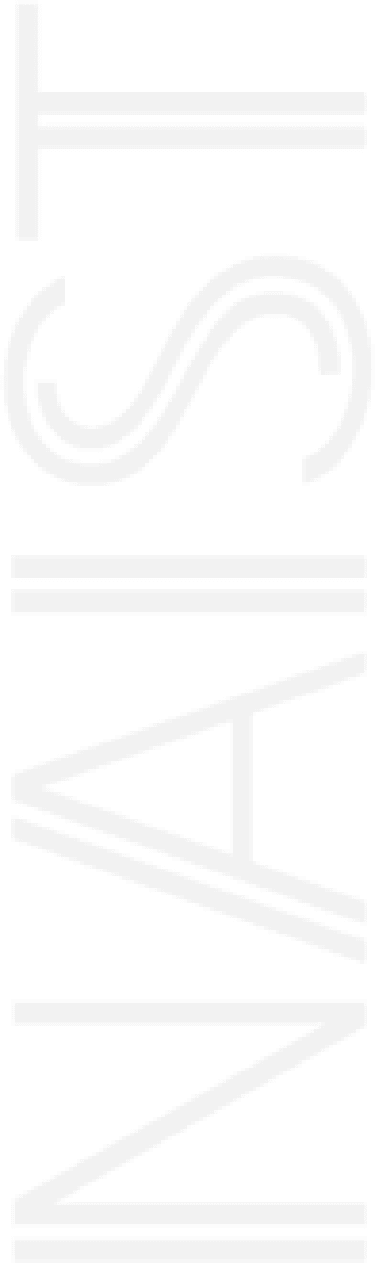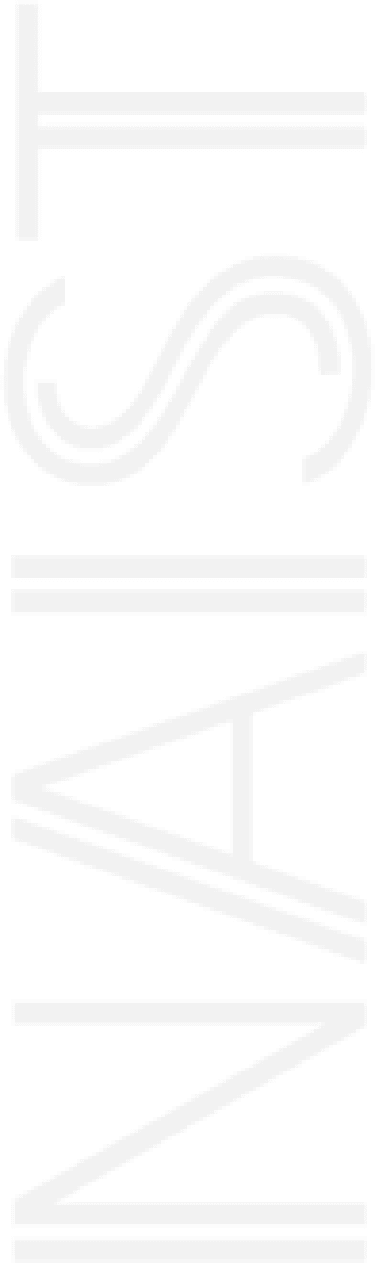ソフトウェアの
信頼性を高める
柏 祐太郎 准教授情報科学領域
ソフトウェア設計学

ソフトウェアの信頼性を高める
柏 祐太郎 准教授情報科学領域
ソフトウェア設計学
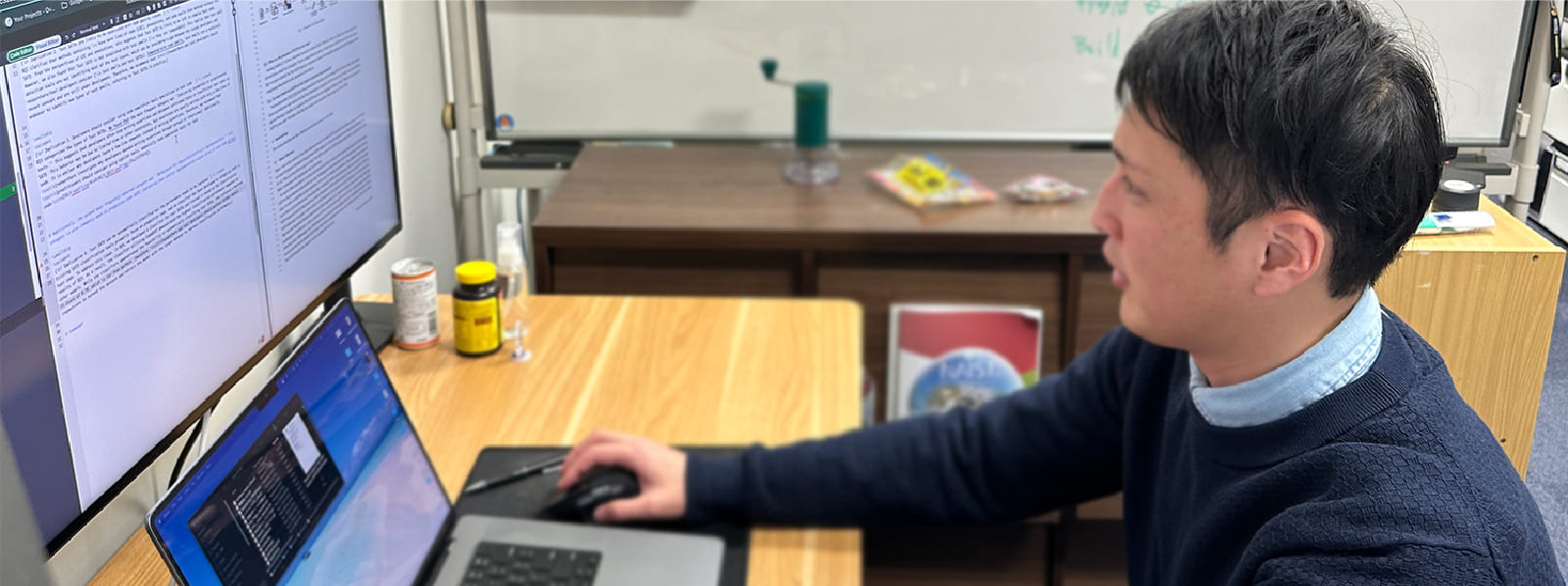
柏祐太郎准教授は、デジタル社会の根幹をなすソフトウェア開発の若手研究者です。
プログラムの不具合の検出、修正を自動化するなど、
ソフトの品質の信頼性を高めるための効率的な手法の研究に挑んでいます。
また、国内外の研究者と積極的に
ネットワークを築き、
共同研究などでグローバルな視野を広げています。
profile

柏 祐太郎 准教授
経歴
-
2013
3月
和歌山大学システム工学部 学士(工学)
-
2015
3月
和歌山大学システム工学研究科 修士(工学)
-
4月
(株)日立製作所 入社
-
2017
3月
(株)日立製作所 退社
-
4月
和歌山大学システム工学研究科博士後期課程 入学
日本学術振興会特別研究員(DC1) 採用 -
2019
4月
カナダ・モントリオール理工科大学 客員研究員
-
2020
3月
和歌山大学システム工学研究科 博士(工学)
-
4月
九州大学大学院システム情報科学研究院 特任助教
-
2021
11月
スイス・スイスイタリア大学 客員研究員
-
2022
4月
本学先端科学技術研究科情報科学領域 助教
-
10月
科学技術振興機構 さきがけ研究員(兼任)
-
2023
9月
オランダ・ラドバウド大学 客員研究員
-
2025
4月
本学先端科学技術研究科情報科学領域 准教授
趣味
サッカー、サッカー観戦、海外旅行、国内旅行、温泉巡り、ラーメン巡り、ボーリング、猫カフェ、料理、カラオケ、テニス、釣り、etc.
interview

現在の研究の内容を教えてください。
科学技術振興機構(JST)の「さきがけ」に採択されたテーマは、ソフトウェアの開発時に、ソフトウェアの振る舞いから、機械が自動的に不具合を検出する手法の構築です。通常は、プログラムを変更し、入力したあと、予測通りに出力されれば、不具合がないと判断します。しかし、それを確認するためには、テストプログラムを作成する必要があり、膨大な工数がかかる上、入出力のチェックだけでは隠れた不具合を見落とすことがあります。そこで、変更前後のプログラムの動きの変化量を定量的に測定するという独自の発想により、テストの工数をかけることなく、的確に不具合を検出する手法を研究しています。
日本学術振興会の「科学研究費助成事業(科研費)」の基盤研究(B)のテーマは、頻発しているシステム運用時に発生した障害を迅速に復旧するため、その原因になったプログラムの不具合を自動的に特定し、修正する手法の開発です。
システムに障害が発生した際には、人手でプログラムが実行された経路などを解析する必要があり、時間がかかります。そこで、ソフトウェアテスト時の実行経路とログを機械学習することで、障害時のログからプログラムの実行経路を推定する技術を開発しています。そして推定した実行経路を再現するテストケースを生成することにより、自動的に不具合を検出・修正するという手法を研究しています。

JSTの先端国際共同研究推進事業「ASPIRE」にはAI関連の研究課題が採択されましたね。
「ソフトウェア開発の文脈を理解したうえで適応するAI技術」というテーマで九州大学と共同研究しています。生成AIもソフトウェア開発に使われ始めていますが、未だ実用的とは言えません。特にソフトウェア開発では、ソースコードを実装する際に様々なコンテキストの配慮が求められます。この研究課題では、空気を読むソフトウェア開発AIを開発することで、より実用的なプログラムを提案し、作業効率の向上に結び付けていきたいと思います。学生においてもAIに対する関心は高く、研究室に所属する学生が倍増しています。この予算は世界と協力しながらAI技術を確立することを目的としており、これから学生を世界に派遣すると共に、海外からも研究者を受け入れて、日本のAI技術の発展に寄与したいと考えています。
これまでの研究に本学の研究環境は役立ちましたか?
ソフトウェア工学の研究では、膨大な数のリポジトリから数十万件にも渡る変更履歴を分析するため、何十時間もかけて行うことが多いです。その点、本学の総合情報基盤センターに全国有数の計算能力を持つ小規模計算システムがあります。これは高性能CPUやGPGPUを搭載したコンピュータが64台連結したクラスタシステムで、高速に並列分散処理ができます。そして、そのシステムは全学共用の設備であるため、無料で使用できます。このシステムにより、本学に赴任するまでは不可能だった膨大な計算量を要する分析や大容量のデータを扱う研究も可能になりました。
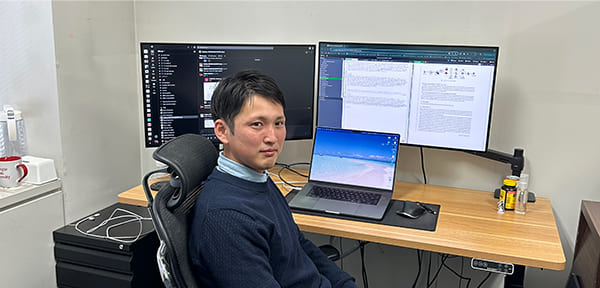
これまでどのような研究の道筋を歩んで来ましたか?
日立製作所でシステムエンジニア(SE)として、流通業のシステム開発に携わる中で「SEでリリースに苦労している人を救うような研究がしたい」と思うようになったのが、研究の道ヘ進むきっかけです。2017年に和歌山大学大学院博士後期課程に入学すると同時に日本学術振興会の特別研究員となり、修了後は九州大学システム情報科学研究院特任助教となり、「重大な影響を起こす不具合」や「コンテクストを考慮したソースコードの改善」について研究しました。そして、2022年に本学に赴任しました。

この間、カナダのモントリオール理工科大学をはじめ、スイス、オランダの3大学で客員研究員を務めていたそうですが、ソフトウェア開発の研究は海外に学ぶところが多いですか?
「日本はハードウェアは強いがソフトウェアは弱い」と当時から言われていて、最近ではデジタル赤字の問題などが表面化しています。「我々若手が日本のソフトウェアの研究を底上げしなければ」との思いから、日本を拠点としながら海外で研究することも考えていました。いまでは、国際学会に参加すると、各国の知人に再会し同窓会のようになります。小学校1年生から高校までサッカーをしていたような体育会系人間なので、コミュニケーションには、自信があります。

国内外のさまざまな大学で研究された経験から、本学をどのように見ていますか?
本学の学生は他大学から入学する学生ばかりなので、志が高く熱心ということは感じます。入学試験も面接や小論文を重視しているので、コミュニケーションやプレゼンテーションの能力に優れ、社会に役立つ自走力を身に付けた人材が入ってきます。海外の大学に近い、よい選考方法だと思います。だから、入学してからも修士課程の2年間でトップ国際会議やジャーナルに投稿する論文が書ける学生も多くいます。
教員にとっては事務作業の負担が比較的少なく、授業や入学試験等の作業負担も少ないため、研究の時間が多く取れるほか、オンラインの学生指導もできるので、海外の学会などに参加しやすいという利点があります。
 若手研究者へのメッセージ
若手研究者へのメッセージ
NAISTの知名度は旧帝大に劣るかも知れませんが、優秀かつモチベーションの高い学生がいることや研究に集中するための時間と環境の観点から、研究を行う環境としては日本屈指だと思います。大学教員のキャリアにおいて、若手の期間に多くの論文を輩出することが期待される昨今では、大学教員の最初のキャリアとしてNAISTは素晴らしい選択肢だと思います。