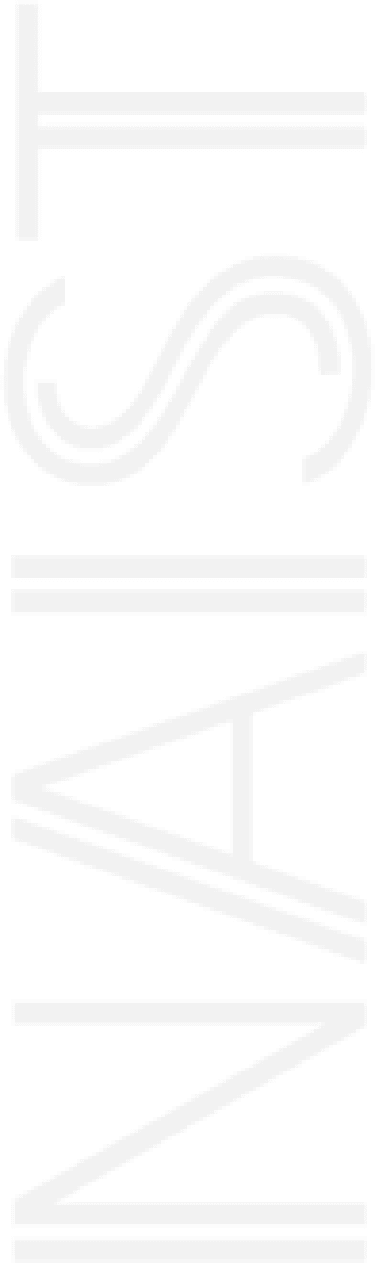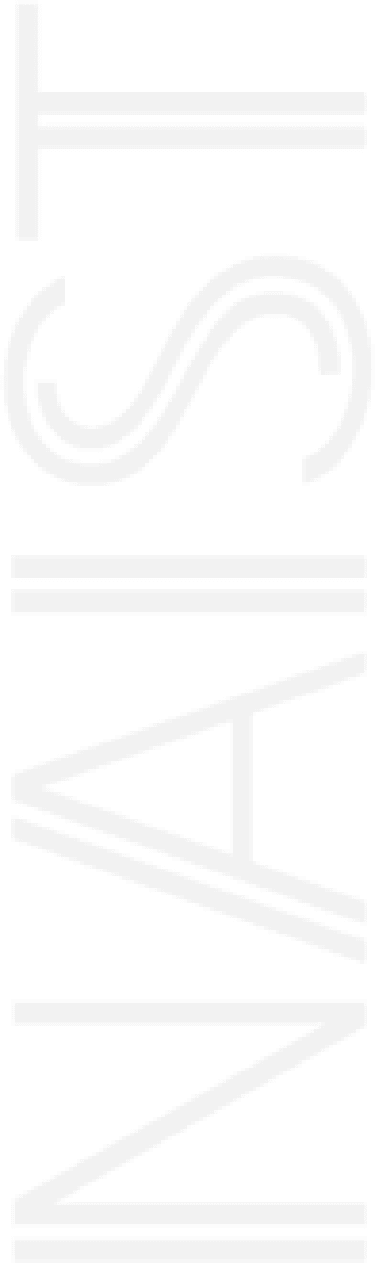次世代の薄膜トランジスタ
製造法を開発
Bermundo Juan
Paolo Soria 助教物質創成科学領域
情報機能素子科学研究室

次世代の薄膜トランジスタ
製造法を開発
Bermundo Juan
Paolo Soria 助教物質創成科学領域
情報機能素子科学研究室

Bermundo Juan Paolo Soria 助教は、柔軟なディスプレイなど
次世代の画像機器やセンサーへの応用が期待される
「酸化物半導体薄膜トランジスタ(TFT)」を高性能化する研究に取り組んでいます。
フィリピンのアテネオ・デ・マニラ大学、本学博士後期課程の出身で、
「研究教育の環境が素晴らしい」と自国の学生にも留学を呼び掛けています。
profile

Bermundo Juan
Paolo Soria 助教
経歴
-
2012
3月
アテネオ・デ・マニラ大学大学院
物理学科修士課程修了 Master of Science -
2015
6月
本学物質創成科学研究科
博士後期課程修了 博士(工学) -
8月
本学物質創成科学研究科 特任助教
-
2020
10月
本学先端科学技術研究科物質創成科学領域 助教
趣味
コンピューター、テクノロジー関係、バスケットボール
休日などは、技術(特にコンピューター、半導体、AI、量子コンピューター)に関する記事や動画を見ています。
週末は大体家族と時間を過ごしています。
interview

どのような目標で研究を進めてきましたか?
日本政府が提唱する「Society 5.0」の未来社会像には、デジタルな空間と強く結びついた人間中心の社会が描かれています。それを実現する電子デバイスの主要部材として酸化物半導体のTFTが注目されていますが、現在の真空下で行う製造法は高コストで、廃棄物など環境に対する「持続可能性」の面で課題があります。そこでわれわれは、すべての工程を低温の溶液中で行って課題をクリアしたうえ、高性能のTFTを製造する方法の開発に挑んできました。
研究の成果を教えてください。
それまでの研究で、TFTに紫外線領域の短い波長のレーザー(エキシマレーザー)を瞬間的に照射すると、薄膜の表面に酸素原子の抜け穴(空孔)が生じ、透明化するとともに、導電性が高まることを発見していました。この現象を応用し、紫外線、レーザー、プラズマ(正イオンと電子が分離した状態)の照射によりTFTの表面に酸素空孔を生成することで、低温の溶液の中で導電性や安定性が高いTFTを作る手法の開発に成功しました。いまは、このTFTを多機能化する研究を行っています。

本学の研究環境についての感想は?
研究室間の壁が低く、日常的に共同研究のように相談できるところがとてもいいと思います。私自身も、異分野の機械学習を学内兼務先のデータ駆動型サイエンス創造センターのミーティングで学んでおり、次の研究に活かそうと思っています。もともと「出会った人との交流を大切にする」が私の信条です。例えば、ある国際学会で私はドイツのレーザー会社のポスター発表に興味を持ち、そこで話をしたことがきっかけで共同研究をすることになりました。その共同研究で出た結果を学会に投稿するなど、実りある成果に至っています。
また、本学は最新の研究設備が多くありますが、担当する技術職員がとても丁寧に説明してくれることはありがたいと思います。研究室も大学の中でも、相手が英語でコミュニケーションを取ろうとしてくれるので、言語の壁というものはあまり感じたことはありません。

アテネオ・デ・マニラ大学から、本学の博士課程に入学されたきっかけは?
アテネオ・デ・マニラ大学物理学部の大学院で修士課程学生として体積ホログラフィック・ストレージと体積ホログラフィック多重化について研究するとともに、物理学科講師として学生に物質科学を教えていました。そのころ、学術交流協定を締結している本学にインターンシップで訪問することがあり、研究科の和気あいあいとした雰囲気を体験し、入学を決意しました。
私は現在、物質創成科学領域で国際広報委員会を担当していますが、学生リクルートなどで母国の大学を訪れた際には、「本学の研究環境はベスト」とアピールしています。

Bermundo助教の妻のジェニファーさんも本学の出身ですね。
アテネオ・デ・マニラ大学で知り合い、共に来日して本学物質創成科学研究科の博士後期課程に入学しました。彼女は量子物性科学研究室(当時)で博士後期課程を修了し、産業技術総合研究所を経て、今は日本の民間企業で研究開発をしています。日本は安全で生活しやすく、本学に学内保育所が開設されるなど子育て支援にも力を入れています。長女は2025年春に日本の公立の小学校に入学しますが、日本語を母国語のように話せ、私の日本語の間違いを直してくれるほどです。
研究室の浦岡行治教授は学内のグリーンラボで熱心に野菜を育てているのですが、年一回、スタッフ、学生で収穫した野菜などをふるまう会を開いてくれます。そのような家族的な気遣いが本学の随所にあり、これも本学の大きなメリットだと思います。
 若手研究者へのメッセージ
若手研究者へのメッセージ
研究者としてのモットーは「科学的な厳密さと公正性を守りながら、好奇心を持ち続けること」です。社会課題を解決しうる研究を、日本で、本学で続けていきたいと考えています。次世代社会に向け、半導体の果たす役割はますます大きくなっています。私は、無駄を省き、低消費電力化を実現することで、半導体技術の持続的な発展に貢献し、私たちの社会を力強く変革し続けることを目指します。
若手研究者には、好奇心を持ち続け、特に他者や社会のために、より多くのことを成し遂げようと常に向上心を持っていてほしいです。このマインドセットを持っていると、研ぎ澄まされた卓越性への情熱を養うことができます。あなたの努力が、現実世界の問題を解決し、社会に有意義な貢献をしたいという願望に突き動かされたものでありますように。