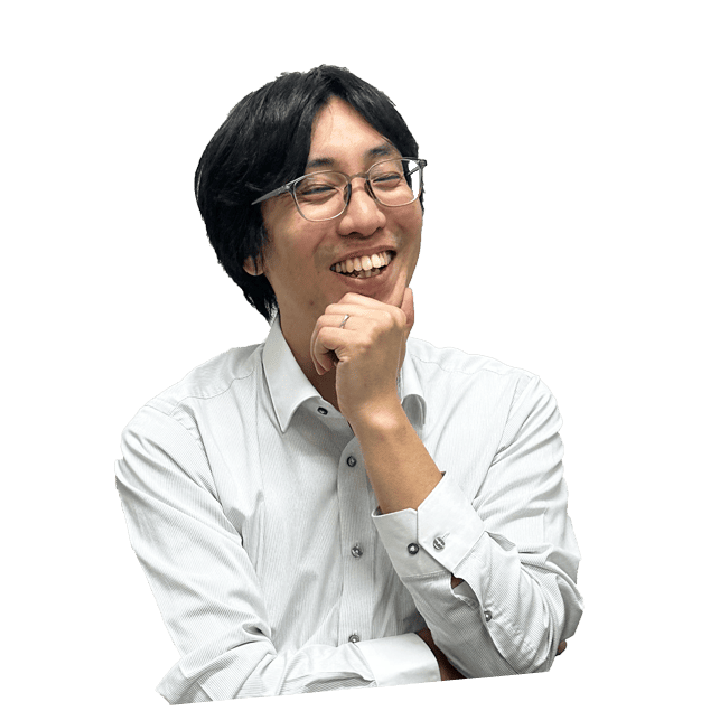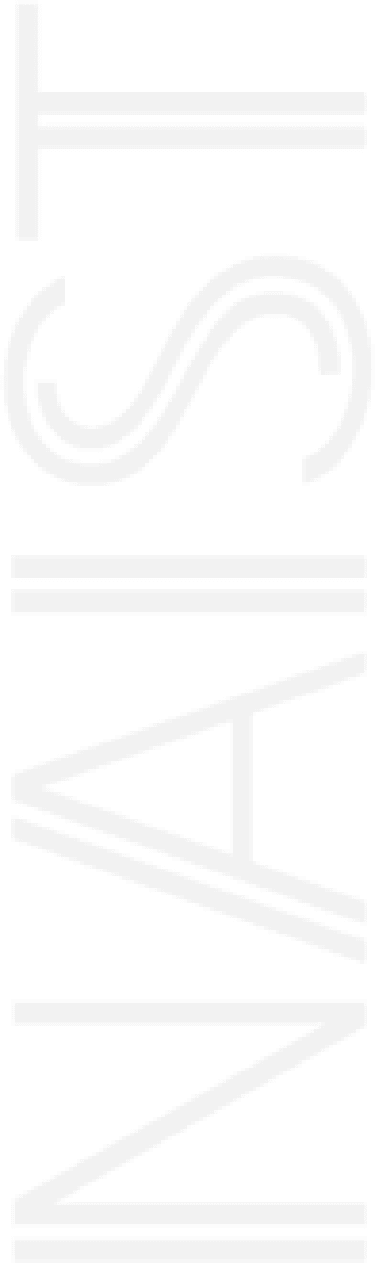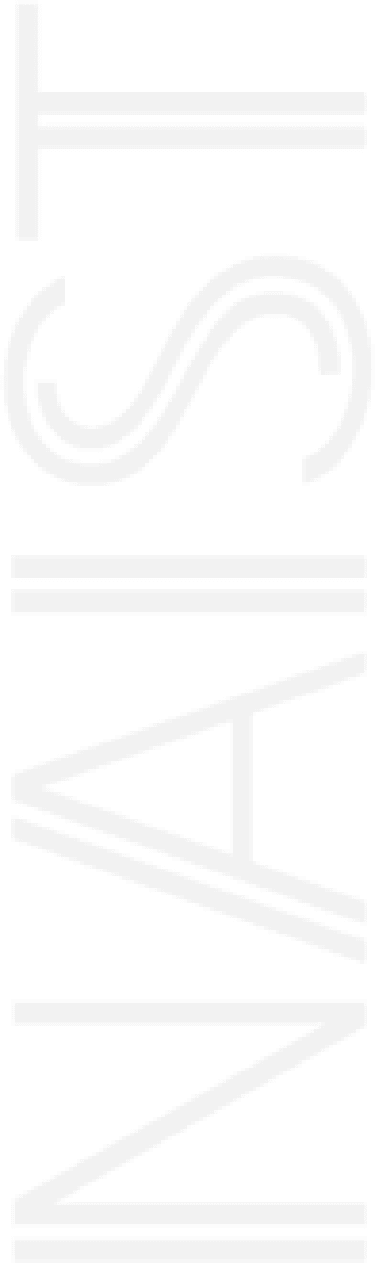融合領域に挑んで道が拓けた
山﨑 将太朗 准教授大阪大学微生物病研究所
奈良先端科学技術大学院大学 客員准教授

融合領域に挑んで道が拓けた
山﨑 将太朗 准教授大阪大学微生物病研究所
奈良先端科学技術大学院大学 客員准教授
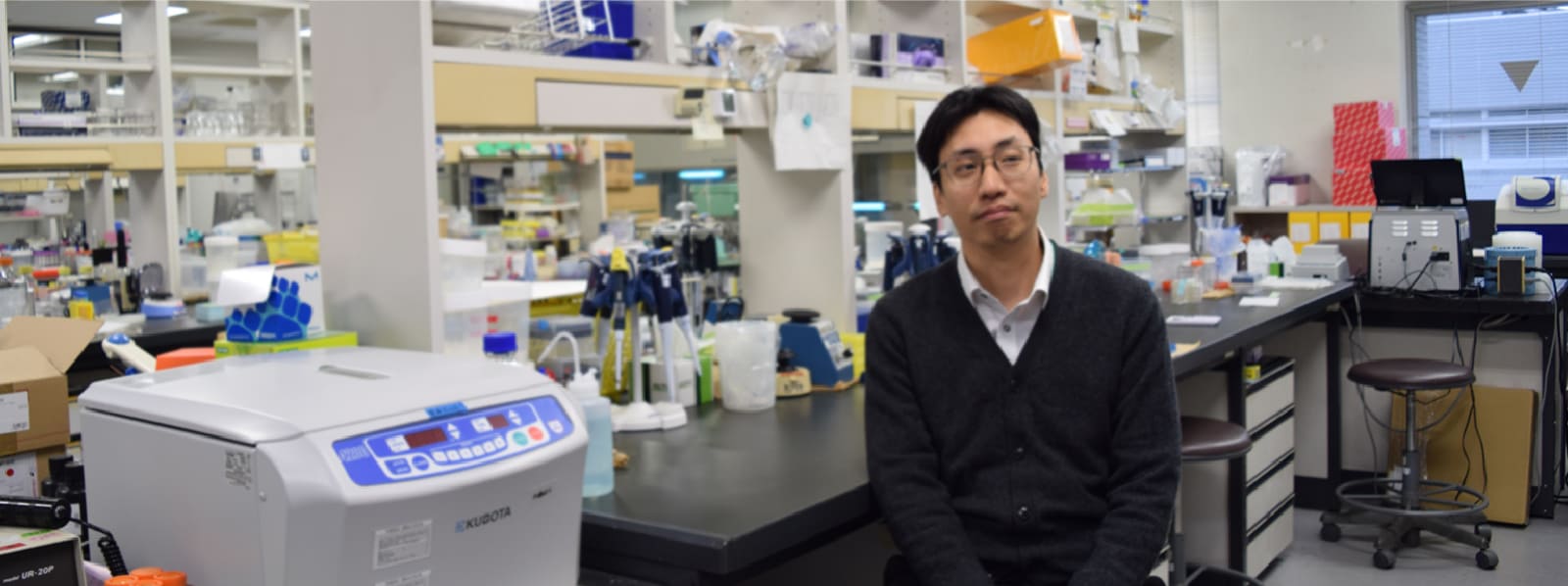
山﨑将太朗先生は、
奈良先端大博士後期課程を修了後、
博士研究員を経て、
バイオサイエンス領域の助教を務め、
現在、本学の客員准教授です。
2024年4月には、新たに大阪大学微生物病研究所附属バイオインフォマティクスセンターの
准教授に就任されました。
profile

山﨑 将太朗 准教授
経歴
-
2016
3月
本学バイオサイエンス研究科博士後期課程修了
博士(バイオサイエンス) -
4月
本学バイオサイエンス研究科 博士研究員
-
2021
4月
本学先端科学技術研究科バイオサイエンス領域 助教
本学デジタルグリーンイノベーションセンター
助教(兼務) -
2024
4月
大阪大学微生物病研究所附属
バイオインフォマティクスセンター生物情報解析分野
RNA情報学グループ 准教授
本学先端科学技術研究科バイオサイエンス領域 客員准教授
趣味
ゲーム
学生時代から、ものづくりやサバイバル、街づくり系のゲームが好きです。
今はゲームをする時間も減り、子どもと一緒に工作やレゴブロックで遊んだり、外で体を動かしたりすることが増えました。ですが、子どもがもう少し大きくなったら、一緒にマインクラフトなどのゲームで遊ぶことを楽しみにしています。
工作
子どもと折り紙や牛乳パック工作をしているうちに、自分のほうが夢中になってしまいました。今では「工作も趣味」と言えるかもしれません。
interview
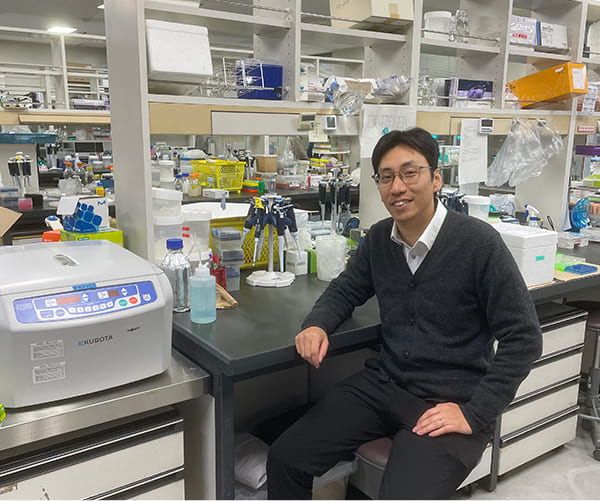
どのようなテーマで研究を続けてきましたか?
私は、メッセンジャーRNA(mRNA)という分子に注目し、細胞の核内にあるDNAの遺伝情報がタンパク質として機能するまでの過程、つまり遺伝子発現の制御機構について研究しています。DNAは生物の設計図ともいえるもので、生物の形や細胞内での分子反応に関わるさまざまなタンパク質の遺伝情報(核酸塩基の配列)がコードされています。特定のタンパク質を作る際には、その遺伝情報を持つDNAの領域だけがmRNAに転写(コピー)されます。この過程では、タンパク質が必要なタイミングで適切な量だけ作られるよう、厳密な調節が行われています。その調節には、mRNAの転写量や、転写されたmRNAにコードされた生産指示の命令文が重要な役割を果たします。私は、基礎研究として、生命活動の根幹をなす遺伝子発現の制御機構を理解するために、mRNAの量を決定する仕組みや、mRNAにコードされた生産指示の命令文の役割を明らかにすることを目指しています。また、応用研究として、そこで得られた知見を活かし、医療用タンパク質などの大量生産技術の開発にも取り組んでいます。DNAという生命の設計図を完全に読み解き、自在に活用することは、現在の情報処理技術をもってしても容易ではありません。私は、その中でもmRNAに記された生物のパーツ単位のシンプルな設計図に焦点を当て、この難題に挑戦しています。

これまでにどのような研究の成果が得られましたか?
タンパク質の生産効率を制御する仕組みにはいくつもの要因が関与しており、その指令書となる情報はmRNA上のさまざまな位置に隠されています。そのため、解析は容易ではありません。そこで、私は独自の手法で取得した大規模データと機械学習を活用し、mRNAの塩基配列とタンパク質の生産効率との関係をモデル化しました。このモデル化により、重要な制御要素の理解が進んでいます。さらに、構築したモデルを応用し、生産効率を向上させる塩基配列の最適化技術を開発しました。この技術では、モデルを用いてmRNAから生産効率を予測し、配列の設計・評価・改良をコンピュータ上で実行することが可能です。これにより、実験の回数を大幅に減らすことができ、研究にかかる時間やコストを大きく削減できます。現在、さまざまな生物種やmRNAの異なる領域に対し、複数の制御過程を考慮した改良を進めています。すでに実用化につながった例もあります。
タンパク質の中には、医療や食品分野で高い利用価値があり、高額なものも少なくありません。例えば、人工培養肉の生産に不可欠な成長因子もその一つです。私は、コムギ胚芽の抽出液を用いた無細胞タンパク質合成系を対象に、高効率なmRNAを設計するシステムを開発し、成長因子の合成コストを低減することに成功しました。この研究は、兵庫県・淡路市の企業との共同研究でした。本学は、研究施設が集積する「関西文化学術研究都市」内に位置することもあり、企業から「研究シーズを使いたい」と共同研究の依頼が多く寄せられています。
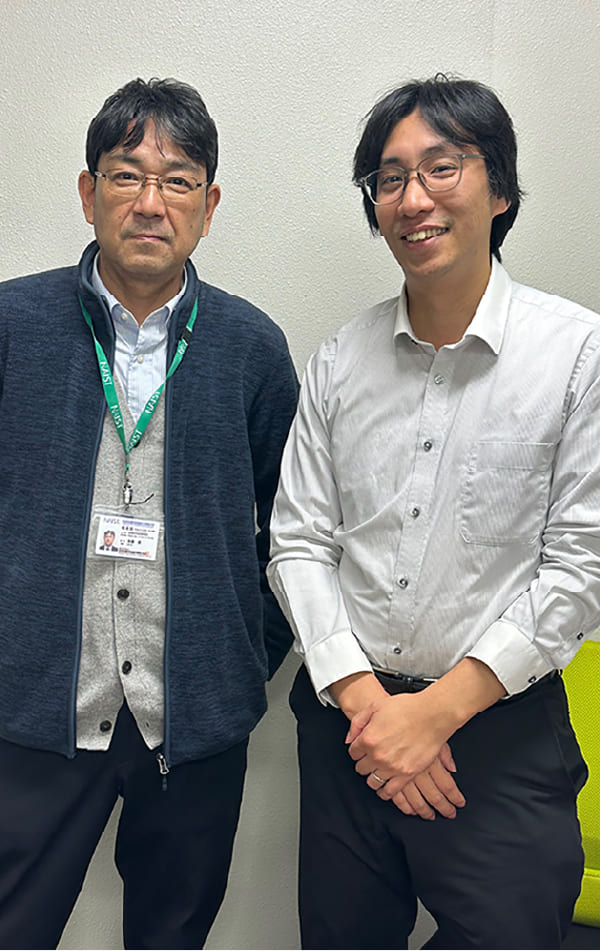
このようなタンパク質生産を予測するモデルの研究手法は、生命現象をコンピュータで解析する「生物情報科学」というバイオサイエンスと情報科学が合体した分野ですが、
異分野の融合を積極的に進めている奈良先端大の研究環境の影響はありましたか?
研究の方向性を決めるほど、大きな影響を受けました。もともと生物学に興味があり、生物系の学科がある工業高等専門学校から神戸大学農学部を経て、奈良先端大に進学しました。博士前期課程までは、いわゆるwet研究(実験を主体とする研究)を行っていましたが、博士後期課程でdry研究(コンピュータ解析を主体とする研究)の「生物情報科学」と出会ったことが、大きな転機となりました。当時私は、植物代謝制御研究室の加藤晃先生(現バイオエンジニアリング研究室教授)のもとで、植物mRNAの翻訳制御に関する研究を行っていました。その過程で、加藤先生が遺伝子の発現量の制御について、過去に情報科学領域の計算システムズ生物学研究室(金谷重彦教授)と共同でデータ解析に取り組んでいたことを知り、未経験の分野に興味を持ったのがきっかけでした。
そこで、金谷先生に基本的な情報科学の技術を教えていただき、データ解析の手法や考え方が自身の研究にも応用できると確信し、本格的にdry研究にのめり込むようになりました。博士後期課程と博士研究員の期間にほぼ独学で情報科学分野の理論やさまざまな研究手法を習得しました。今では「生物情報科学」が私の主要な研究分野です。学生時代に融合領域の研究に打ち込み、新たな研究のバックグラウンドを築けたことは今に活きています。
教員の立場から見ても、私のように異分野融合に挑戦する学生がいることは、研究環境に良い刺激をもたらすと感じます。もし自惚れでなければ、私の学生時代は、指導してくださっていた加藤先生の研究アプローチにも影響を与え、互いに切磋琢磨できる関係だったと思います。
このような経験から、次世代の融合領域の研究を推進する本学のプロジェクトは、学生にも教員にも非常に良い経験になると実感しています。現在では、NAIST Granite Programやデジタルグリーンイノベーションプログラムがあり、私の時代よりも学生が融合領域を学べる機会が増えています。私も指導する学生には、積極的に参加するよう勧めています。さらに、教員同士の異分野融合を支援する次世代融合領域研究推進プロジェクトなどの制度もあります。このような支援があることで、互いに興味を持つ研究者同士がマッチングし、質の高いデータを取得しながら十分な検証を行うことが可能になり、お互いにメリットのある研究へと発展していきます。異分野融合による研究の発展を目指すならば、奈良先端大は非常に恵まれた環境にあると言えるでしょう。

本学で学生と教員双方の立場で十数年過ごされていますが、研究や教育の環境についてどのような感想を持っていますか?
研究と教育のバランスが非常に良い大学だと感じています。奈良先端大は学部を持たない大学院大学のため、学部生が在籍する一般的な大学と比べて学生数が少なく、研究への意欲が高い学生が多い印象です。修士課程以上の学生が中心のため、研究のレベルも高く、少数精鋭のラボを形成することが可能です。「教員一人当たりの学生数の少なさ」は全国でもトップクラスであり、その分、学生にとっては充実した指導を受けることができます。教員にとっても、学生指導の負担と研究へのプラスの効果のバランスが取れた環境になっていると感じます。また、バイオサイエンス領域では、自分が所属する研究室の指導教員だけでなく、他の研究室の教員がアドバイザーとして修士論文や博士論文のサポートを行う仕組みがあります。このアドバイザーヒアリングを通じて、普段なかなか話す機会のない教授クラスの先生方から、自分の研究に役立つ貴重な意見をいただいたこともありました。
また、大学院大学であるため、学部のある大学と比べて講義の数は少ないです。一方で、大学教員としてキャリアアップするためには、研究だけでなく教育の実績も重視されます。バイオサイエンス領域には、手を挙げれば最先端の研究トピックスとして自分の研究を紹介できる講義など、1コマ単位で担当できるような講義もあります。そのため、教育実績のない新任教員でも少ない負担で講義の経験が持てます。研究と教育のバランスを取りながら実績を積むには、とても良い環境だと思います。
さらに、奈良先端大では、学生、教員に対し、低価格の家賃で居住できる大学宿舎が大学の近くに用意され、時間の制約なく研究にまい進できる環境が充実していることなども研究生活の支えになりました。
 若手研究者へのメッセージ
若手研究者へのメッセージ
研究は一人で進められるものではありません。もちろん、学生の指導は大変なこともあります。しかし、奈良先端大に集まる学生は、修士課程や博士後期課程です。「教えるだけ」ではなく、学生と教員で「高め合える」素敵な関係を築くことがきっとできます。研究員や技術職員を雇える余裕がない若手研究者にとって、こうした優秀な学生との出会いは大きな財産になります。奈良先端大は、研究と教育のバランスが取れており、設備も整っています。この環境のもとで、研究と教育の両方を確実にステップアップできるはずです。私は学生時代から助教まで過ごした奈良先端大が大好きです。力ある若手研究者の皆さんには、ぜひ奈良先端大に来ていただき、この大学をさらに盛り上げていってほしいと思います。