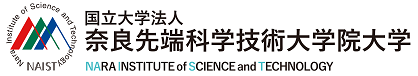講座日程等
2025年10月11日(土)
| 13:45~15:00 |
「南極って寒いだけじゃない!?観測隊の仕事と暮らし」 管理部 企画総務課 企画・法規係 |
|---|---|
| 日本から約14,000㎞離れた場所にある、南極の昭和基地。ペンギンやアザラシ、オーロラなど南極ならではの大自然に囲まれると同時に、マイナス30度を下回る日もある、過酷な環境です。そこで活動する南極地域観測隊は、どのような人たちなのでしょうか。極地で活躍する隊員たちと、南極での暮らしをお伝えします。 | |
|
「アフリカの学校ってどんなところ?」 教育推進機構 キャリア支援部門 |
|
| タンザニアという国を知っていますか?アフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ山に、ライオンやゾウ、キリンなど多様な動物たちが共生する大自然。そこにある中学校で、数学を教えていた先生の体験をお話しします。日本の生活ではなかなか知ることができないアフリカの自然や、学校の様子をのぞいてみましょう。 | |
| 15:15~16:30 |
「PD-1: がん治療に革命を引き起こした分子」 バイオサイエンス領域 機能ゲノム医学研究室 |
|
今から34年前、私は京都大学の本庶佑研究室にて興味深い分子を発見し、PD-1と命名しました。今世紀に入り、抗体によって体内でPD-1の機能を弱めてやると一部のがんが治ることが発見され、2018年には本庶教授にノーベル生理学医学賞が授与されました。本講義では、PD-1とがんの関係について議論します。 |
2025年10月18日(土)
| 13:45~15:00 |
「老いを科学する 〜細胞から見た老化のしくみ〜」 バイオサイエンス領域 遺伝子発現制御研究室 |
|---|---|
|
私たちはなぜ老いるのでしょうか?細胞や遺伝子レベルで進む"老化"の仕組みを科学的にひもとき、健康長寿の延伸へ向けたヒントを探ります。本講義では、私たちの最新研究を含めた「老い」の真実についてご紹介します。 |
|
| 15:15~16:30 |
「細胞の形の謎を解く:細胞突起と細胞外小胞」 バイオサイエンス領域 分子医学細胞生物学研究室 |
|
私たちの体を構成する細胞は、様々に形を変化させて、機能します。例えば、突起を出して移動し、突起を切断して細胞外小胞を分泌します。一方、形の制御が異常になると、がんなどの病気を引き起こすことが分かってきました。それでは、細胞の形はどのように制御されるのでしょうか。本講義ではその謎に迫ります。 |
2025年10月25日(土)
| 13:45~15:00 |
「身近な体内時計 植物から私たちまで」 バイオサイエンス領域 植物生理学研究室 |
|---|---|
|
「体内時計」という言葉を耳にしたことのある人は多いでしょうが、それが植物からヒトにいたるまで、どのように役立っているかについて知っている人は意外と多くありません。植物の話を中心としながらも他の生き物の体内時計についても触れつつ、生物の中で時を刻む体内時計の不思議さ・おもしろさを紹介します。 |
|
| 15:15~16:30 |
「根を張る―細胞の振る舞いから探る植物の成長戦略」 バイオサイエンス領域 植物発生シグナル研究室 |
| 植物の根は、周囲の環境に応じて成長の方向や分岐のパターンを変えながら、土の中で巧みに広がっていきます。その背景には、分裂・伸長・分化といった細胞の緻密な振る舞いが関わっています。本講義では、根の成長を支える細胞の振る舞いに注目し、植物がどのように根を張るのか、その仕組みを紐解いていきます。 |