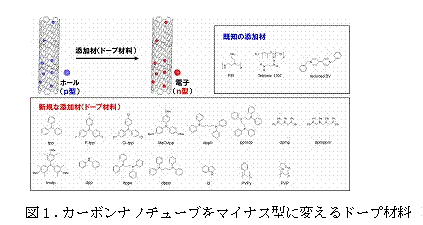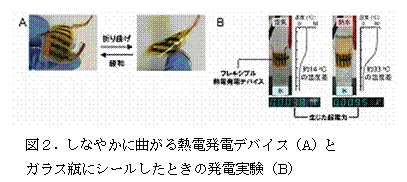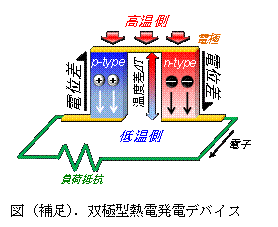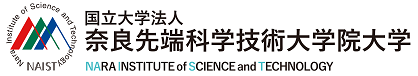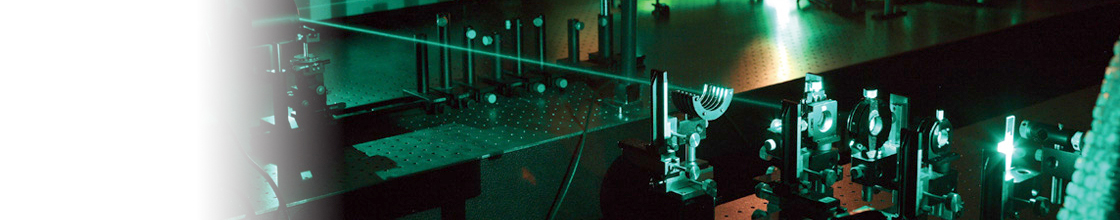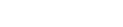2013/11/27
【概要】
奈良先端科学技術大学院大学(奈良先端大、学長:小笠原直毅)物質創成科学研究科光情報分子科学研究室の河合 壯(かわいつよし)教授、野々口斐之(ののぐちよしゆき)助教らは、配管やホースなどの曲面にぴったりと実装でき、排熱の温度差により発電する高性能の熱電発電シートの開発に世界で初めて成功しました。
こ の技術を使い試作した熱電発電デバイス(装置)は、柔軟で、熱源に貼るだけで発電できることから、工業プラントの配管や複雑な形状をもつラップトップコン ピューター等の排熱を利用して電力を再生する方法や、体温を利用した健康モニター用電源など、省エネや地球温暖化の抑制に貢献するアプリケーションが期待 されます。
今日、消費されるエネルギーのうち約3分の2が未利用のまま環境中に出されています。その排熱の80%以上は200℃以下であ り、また、持ち運びする排熱環境での使用が多いため、従来のタービンなどの大規模設備に用いることはできませんでした。そこで、熱回収と電力再生が効率的 な柔らかい熱電発電デバイスが望まれています。これまでにフレキシブルなプラス型(p型、低温側がプラスに帯電)の熱電材料には導電性ポリマーやカーボン ナノチューブなどが提案されてきましたが、マイナス型(n型、低温側がマイナスに帯電)の熱電材料を組み合わせて理想的な双極型熱電発電シートを開発する ことが高効率の熱電変換には必要とされてきました。しかし、フレキシブルなマイナス型の熱電変換材料はこれまで開発されておらず、世界中の研究者が検討し てきました。
河合教授らは、軽くて丈夫なカーボンナノチューブに着目し、その熱電発電特性について研究を重ねました。その結果、通常はp 型を示すカーボンナノチューブを安定なn型に変える一連の薬剤(ドープ材料)を発見し、非常に困難とされていたフレキシブルなn型熱電変換材料の開発に成 功しました。さらに、この材料を使ってプラス型にもマイナス型にも変えられるフレキシブルな熱電発電シートを試作し、これが曲面上でも発電し、十分な電力 を回収できることを実証しました。この成果は、英国ネイチャー・パブリッシング・グループのオンライン総合科学雑誌「Scientific Reports(サイエンティフィック・リポーツ誌)」に掲載される予定です(プレス解禁日時:日本時間 平成25年11月26日(火)午後7時)。
【背景】
今 日、先進国で消費されるエネルギーのうち約3分の2が未利用のまま排熱として環境中に出されています。その1%でも無駄なく回収できれば、地球温暖化の抑 制や省エネに大きな効果が見込めます。大規模な熱源としては火力・原子力発電所や自動車の排熱などがあり、さらに温泉や私たちの人体そのものもエネルギー 資源となり得るのです。しかし、これらの排熱の80%以上は200℃以下であり、しかも大概は分散しているため、タービンを回して発電するような従来型の 技術によるエネルギー回収は考えられませんでした。
このような環境中に放出される熱エネルギーを直接電力に変換する技術が熱電変換です。 利用されずにむしろ邪魔になる排熱を電気エネルギーに換えられる技術として注目を集めています。温度差がある限り電力が得られるため、電池交換や配電、停 電の時期を意識する必要はありません。可動部を持たないため騒音が無く地震などに対しても強靭です。しかも排出ガスがないため、クリーンな電気エネルギー を得ることが可能です。二酸化炭素の排出を抑制できるほか、エネルギーの原子力への依存度も下げることができます。
こうしたことから、効率的な熱回収のためには熱源の形状に合わせて密着できるフレキシブルな熱電発電シートの開発が待たれてきました。
【技術課題】
従 来研究されてきた熱電変換材料の多くは、鉛、ビスマス、テルルなどの希少金属を主な原料として作製されているため、素子材料の低コスト化や大量普及が困難 な状況にあります。また、これらは金属や半導体であるため、柔軟性に乏しく、曲面に密着させることが困難です。こうしたことから、大半の廃熱・放熱源に設 置することは難しいと考えられており、これらの材料の特性である安定性や耐熱性を活かした高温の熱源での使用に限定されています。
そこ で、近年、比較的低温の排熱をターゲットにして、導電性高分子やカーボンナノチューブを使用したフレキシブル熱電変換材料の研究が行われてきましたが、こ れらはいずれもプラス型(p型)材料に限定されていました。効率的な電力変換のためには効率の良いフレキシブルなマイナス型(n型)熱電変換材料を開発 し、両者を組み合わせて双極型熱電発電シートを開発する必要がありました。
【研究の経緯・結果の概要】
河合教授らの研究グループ は、軽くて丈夫なカーボンナノチューブに着目し、その熱電発電特性を検討してきました。その結果、通常はp型を示すカーボンナノチューブを安定なn型に変 えるために添加する一連の薬剤(=ドープ材料)を発見し、とくに困難とされたフレキシブルなn型熱電変換材料の開発に成功しました。さらに、今回開発した カーボンナノチューブ材料をプラス型とマイナス型材料の両方に使うことでフレキシブルな熱電発電シートを試作し、これが実際の曲面上でも発電動作し、十分 な電力を回収できることを実証しました。
今回の複合材料は、母材としてフレキシブルであるとともに比較的高い導電性がある単層カーボンナ ノチューブを用いました。図1を含む33種類の化合物を添加剤(ドープ材料)として調査することにより、単層カーボンナノチューブがマイナス型(n型)材 料になるかどうかを調べました。
その結果、リン化合物誘導体を含む18種類のドープ材をカーボンナノチューブと組み合わせた場合に、カー ボンナノチューブがマイナス型(n型)に変化することを発見しました。n型熱電変換材料としての熱電変換特性を示す条件を最適化して調べたところ、単位温 度差あたりの発電電力に相当するパワーファクターは約30(μW/K2m)と見積もられました。これは1mm当たり100度の温度差があるときに、 1cm2の面積でおよそ30mWの電力を生み出すことに相当します。
最後に、プラス型とマイナス型のカーボンナノチューブシートを組み合わせ、双極型熱電発電シートを試作し、実験したところ、実際の曲面上でも期待通りの熱電発電の動作があることを証明しました(図2)。
今 回の研究では産業技術総合研究所で開発されたスーパーグロース・カーボンナノチューブを用いることで優れた柔軟性を有するシートを実現しています。また、 九州大学の安達千波矢教授、奈良女子大学の棚瀬知明教授らのご協力により、詳細なメカニズム等についても解明することができました。
【今後の展望】
今 回試作した熱電変換シートは、世界で初めての双極型のフレキシブル熱電変換シートです。例えば、100平方メートルのスケールで敷設すると、キロワットか らメガワット程度の出力を得ることも可能になりました。このシートにより、温泉、火力発電所や焼却・燃焼設備など様々な熱源を持つ設備、自動車から出る排 熱を有効利用できれば、化石資源の効率的な利用と地球温暖化の抑止を同時に達成する切り札になると期待しています。今後は、製造プロセスやコストと耐久性 のバランスなどについて早急に検討を行い、早ければ5年程度で実用化にこぎ着けるように研究を加速させたいと考えています。
【研究支援】
今回の研究は奈良先端科学技術大学院大学の文部科学省特別経費「グリーンフォトニクス研究教育推進拠点整備事業」および科学研究費補助金・研究活動スタート支援(No. 23810021)および新学術領域研究「配位プログラミング」の支援を受けました。
【共同研究】
本研究の実施においては、産業技術総合研究所・畠賢治博士、九州大学・安達千波矢教授・中川哲也助教、奈良女子大学・棚瀬知明教授らのご協力をいただきました。
【発表論文】
Y. Nonoguchi, K. Ohashi, R. Kanazawa, K. Ashiba, K. Hata, T. Nakagawa, C. Adachi, T. Tanase, T. Kawai,
"Systematic Conversion of Single Walled Carbon Nanotubes into n-type Thermoelectric Materials by Molecular Dopants"
Scientific Reports (印刷中)
【補足・キーワード解説】
熱 電発電・熱電変換:金属や半導体試料の両端に温度差をつけることにより、その両端間に電圧が発生するという「ゼーベック効果」の理論を応用した発電を熱電 発電、その変換方法を熱電変換と呼ぶ。素子の一方を高温の熱源に接触させ、他方を低温の熱浴(例えば水冷や空冷された熱浴)に接触させることで、温度差を 作り出し発電することができる。電圧は温度差に比例して大きくなる。
熱電変換材料のプラス型(p型)、マイナス型(n型):高温側に対し低温側でプラスの電圧が発生する材料はp型材料(プラス型)、マイナスの電圧が発生する材料はn型材料(マイナス型)と呼ばれる。
ドー プ材料:半導体に少量の不純物を添加することをドーピングといい、添加する不純物をドープ材料(ドーパント)と言う。半導体製造では特に重要な操作で、不 純物の種類とその量を変えることにより、半導体の導電性を制御することができる。カーボンナノチューブの場合も適切なドーパントを導入することにより、n 型とp型の制御ができるのではないかという発想が、今回の成果につながった。
双極型熱電発電デバイス:プラス型(p型)とマイナス型(n 型)の材料を直列に組み合わせて、両者の接点部分を高温熱源に接触させることで熱電変換効率を大幅に改善することができる。ギリシャ文字のπ(パイ)の形 をしているため、「π型構造」とも呼ばれる。実際の素子は、この「π型」をいくつも並べて電気的に接続して平板状やフィルム状に形成される。プラス型(p 型)もしくはマイナス型(n型)だけを利用する単極型熱電発電デバイスは熱の利用効率が低く、実用には向かないとされる。
単層カーボンナ ノチューブ:カーボンナノチューブは炭素原子のみからなり、直径が0.4~50 nm、長さがおよそ1~数10 µmの1次元性のナノ材料である。その化学構造はグラファイト層を丸めてつなぎ合わせた形で表され、層の数が1枚だけのものを単層カーボンナノチューブ、 複数のものを多層カーボンナノチューブと呼ぶ。本研究では産業技術総合研究所から提供されたスーパーグロース法によって合成された単層カーボンナノチュー ブであるスーパーグロース・カーボンナノチューブを利用している。この合成法は化学気相成長(CVD)法の1種で、水分を極微量添加することにより、触媒 の活性時間および活性度を大幅に改善した方法。
ウェアラブルデバイス:衣服や装飾品と同じように身につけられるほど小型のコンピューターやデバイス。軽量でかさばらず、折りたたんだり、広げたりできるもの、衣料品の一部に組み込んだものなどが試作されている。小型かつ軽量の電源の開発は実用化の重要な技術要素である。
【関連リンク】
・論文は以下に掲載されております。
http://dx.doi.org/10.1038/srep03344