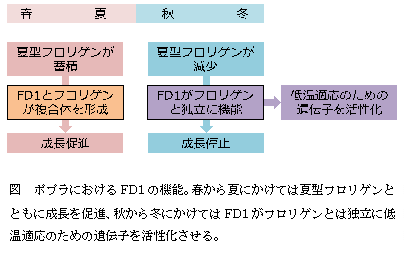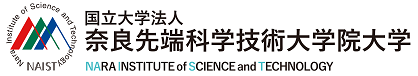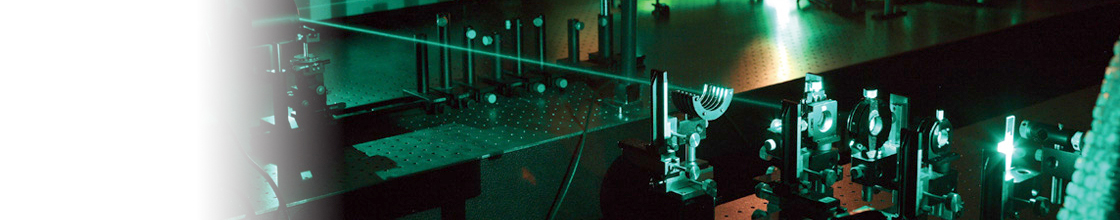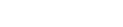2015/03/10
【概要】
花を咲かせる植物ホルモン「フロリゲン」が花芽以外のジャガイモの形成にも役立つなど多機能な性質があることがわかってきた。その多機能性に関連してフロリゲンとともにDNA上に結合して働くタンパク質「FD」にもポプラの成長を促進するなど重要な機能があることが、奈良先端科学技術大学院大学(学長:小笠原直毅)バイオサイエンス研究科植物分子遺伝学研究室の辻寛之助教、(故)島本功教授、スウェーデン農業科学大学・ウメオ植物科学センターのRishikesh P. Bhalerao(リシケシュ・バレラオ)教授らの共同研究で初めて発見された。FDは夏の間にフロリゲンとともにポプラの成長を促進し、秋以降はフロリゲンとは独立して低温耐性の獲得に働くというもので、多機能性の謎を解くカギになると見られる。
フロリゲンは葉で合成されたのちに茎の先端まで移動し、受容体と呼ばれるタンパク質にキャッチされた後、FDと呼ばれるタンパク質とともにDNA上に結合して機能している。最近になってフロリゲンは花芽形成以外にもジャガイモ形成や玉ねぎ形成など驚くべき多機能性を示すことが明らかになったものの、なぜフロリゲンが多様な機能を示すのか、またそこでFDの機能が必要なのか、その原因は分かっていなかった。
そこで研究グループはポプラが越冬する際の生理応答に注目して解析を行った。
ポプラは夏季と冬季の2回、フロリゲンを合成する。冬季に合成された冬型フロリゲン(FT1)は花芽形成を開始させるが、一方で夏季に合成された夏型フロリゲン(FT2)は花芽形成ではなく成長を促進させる効果をもつ。ポプラは秋以降に生長を停止して低温をやり過ごすが、この生長停止は夏型フロリゲン量が秋以降に減少することで引き起こされることが知られている。
研究グループは夏季のフロリゲンによる成長促進にFDが関与しているかどうかを調べるために、ポプラのFDを詳しく調査した。ポプラはFD1とFD2の2種類のFDを持っており、興味深いことに、FD1とFD2のどちらもフロリゲンと複合体を形成できるにも関わらず、FD1だけが機能を発揮できることを特定した。FD1は夏型フロリゲンと複合体を形成してポプラの成長を継続させる。
さらに、夏型フロリゲンの量が秋以降に減少した際のFD1の機能を調べた。詳細な解析から、夏型フロリゲンが減少した後、FD1はフロリゲンに関係なく、冬季の低温に対する適応を促進する遺伝子を活性化させることが明らかとなった。これらの結果を総合すると、春から夏にかけては夏型フロリゲンとFD1がともに機能することでポプラの成長を促進し、秋以降に夏型フロリゲンの量が減少すると、FD1単独の機能が発揮され、冬の低温に備えるための遺伝子が活性化されると考えられる。
この成果は、平成27年2月23日付けで米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)の電子版に掲載された。
論文タイトル: " Dual role of tree florigen activation complex component FD in photoperiodic growth control and adaptive response pathways."
論文著者:*Szymon Tylewicza, *辻 寛之(*共同筆頭著者), *Pál Miskolczia, Anna Petterlea, Abdul Azeeza, Kristoffer Jonssona, 島本 功, and Rishikesh P. Bhalerao
【研究背景】
フロリゲンは植物に花芽を作らせる決定的な効果を持つ植物ホルモンである。葉で作られ茎の先端に移動して効果を発揮する。その正体は長い間謎であったが、2007年に、(故)島本教授らが「FT」もしくは「Hd3a」と呼ばれるタンパク質であることを突き止めた。2011年には茎の先端でフロリゲンをキャッチする受容体も発見された。2015年2月にはフロリゲンが茎の先端に分布する様子が精密に撮影された。フロリゲンはFDが受容体及びDNA結合タンパク質FDとともに「フロリゲン活性化複合体」を形成し、花を咲かせる遺伝子を活性化させる。
最近になって、フロリゲンが花芽形成だけでなくジャガイモ形成など様々な機能を有することが明らかになってきた。しかし、花成と無関係な現象にFDを始めとするフロリゲン活性化複合体が関与しているのかは分かっていなかった。ポプラにおいては、2種類のフロリゲンが夏季の生育促進と冬季の花芽形成をそれぞれ担っていることが知られている。特に夏季の生育促進は花と無関係の現象であり、ここにFDが関与するのかを詳細に研究した。
初めに研究グループはポプラから2種類のFD(FD1及びFD2)を発見した。細胞内でこれらのFDとフロリゲンを合成させたところ、FD1は下流の遺伝子を活性化する機能を有するが、FD2はできないことが分かった。したがって、FD1はフロリゲンとともに機能するFDであると考えられる。そこでFD1の合成量を変化させたポプラの成長を調査したところ、FD1を減らすとフロリゲンが減った場合同様成長停止が早まり、逆にFD1を増やすとフロリゲンを増やした場合同様に成長が促進されることが分かった。さらにFD1の量を増加させたポプラでは低温適応のための遺伝子がより強く活性化していることが分かった。一方で、FD2の量を増加させると植物が矮小化したため、FD2はフロリゲンとは無関係に成長を抑える機能があると考えられた。
【研究の位置づけ】
ポプラには2つのFDが存在するにも関わらず、フロリゲンとともに機能できるのはそのうち一つだけであることを初めて特定した。さらにポプラにおいてFDが2つの機能、すなわちフロリゲンに依存して夏季の生育を促進する機能と、フロリゲンに依存せずに低温適応のための遺伝子を活性化させる機能を持つことを初めて明らかにした。これらはフロリゲンがFDとともに働く仕組みを解明する上で重要な発見と言える。
この発見からは、フロリゲンだけでなくFDの改変によってもポプラの成長と低温適応を操る技術を開発できる可能性があり、有用な樹木の増産へ向けた貢献が期待される。
【補足説明】
●フロリゲンとは
花芽を作らせる決定的な効果を持つ植物ホルモンであり、FTもしくはHd3aと呼ばれるタンパク質がその正体である。奈良先端科学技術大学院大学・植物分子遺伝学研究室においてこれまで、フロリゲンの正体がHd3aと呼ばれるタンパク質であることが証明され(2007年 Science誌にて報告)、フロリゲンがはたらく際の受容体が同定され(2011年 Nature誌に報告)、またフロリゲンが花だけでなくジャガイモを作ることが示された(2011年 Nature誌に報告)。2015年2月にはフロリゲンが茎の先端に分布する様子が精密に撮影された。
●FDとは
フロリゲンとともに働くDNA結合タンパク質。京都大学の荒木崇教授のグループがドイツの研究グループと同時に発見した。奈良先端科学技術大学院大学・植物分子遺伝学研究室においてイネのFDの詳細な解析が行われ、FDがフロリゲン及びフロリゲン受容体と結合してタンパク質複合体「フロリゲン活性化複合体」を構築して機能することが示されている(2011年 Nature誌に報告)。