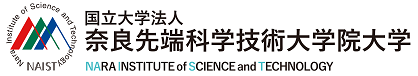読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~
第53回:バイオサイエンス研究科 細胞シグナル研究室 塩﨑一裕教授 〔2017年10月18日〕
「異分野と融合 発見の道筋」

芸術やスポーツと同じように、科学研究も世界で共有できる、人類の営みの一つです。各国で科学者は様々な研究を進めていますが、国境を超えて協力、あるいは競争しながら、科学は発展しています。
母国を離れて研究に取り組む科学者もたくさんいます。Jリーグに所属する外国人選手や、海外のクラブチームで活躍する日本人選手がいるのと似ています。
私の研究室は、米国のカリフォルニア大でスタートしました。がんや糖尿病などの病気の原因となる細胞の仕組みの解明を目指しています。人の健康に役立つ研究を目指しているのですが、酵母菌の細胞を使うのが特徴です。
ヒトの細胞は分裂するのが遅く、実験に必要な数を集めるのに時間がかかるのが難点です。対して、酵母は増殖が速いので、研究を素早く進めることができるというわけです。
酵母とヒトは全く違うように見えますが、実は細胞のレベルで見ると、生命の営みに関わる働きは驚くほどそっくりです。酵母の細胞で発見したことは、たいていヒトの細胞にも当てはまります。
米国の大学ですから、一緒に研究するのも授業で教えるのも、もちろんアメリカ人の学生たちでした。20年近く過ごした後、日本の若い人たちとも一緒に研究してみたいと思い、数年前に奈良先端科学技術大学院大に研究室を移しました。
奈良先端には学部がなく、他の大学の学部を卒業した学生が進学する「大学院大学」です。米国では、卒業した大学の大学院に進む人は少なく、他大学に進学して異なる環境と教授陣からより多くのことを学ぶという考え方が主流です。大学院大学という制度は米国流と言えるかもしれません。