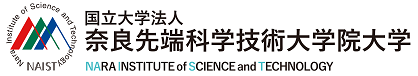読売新聞寄稿連載「ドキ★ワク先端科学」から~
第56回:バイオサイエンス研究科 植物免疫学研究室 西條雄介教授 〔2018年1月17日〕
「植物の免疫 常在菌を監視」

植物を生活の糧にしているのはヒトだけではありません。細菌やカビなどの微生物も植物に寄生して増殖し、時に病気を起こします。植物の病虫害は甚大で、世界で年間10億人以上の食糧に相当する分が失われています。
一方で、植物には病原体に対抗する優れた免疫システムがあり、病気の発生をやすやすと許すわけではありません。動物の免疫と比較してみましょう。
ヒトなどの脊椎動物は、顎が発達するにつれ、様々な植物を取り入れるようになりました。体内に侵入する病原体も多様化し、対応するため多彩な抗体を生み出せるよう進化しました。これが獲得免疫です。
植物にはこうした仕組みは見当たりません。生まれつき備わったシステムだけで、無限に進化する多様な微生物に立ち向かいます。
侵入した微生物の構成成分や、自らの細胞の異常を検知するアンテナの役割をする免疫受容体を働かせて、大半の感染を防いでいるのです。病原菌が入り込むには、免疫受容体に検知されないよう細胞の成分を変化させたり、タンパク質や毒素を注入して免疫システムを撹乱したりすることが必要です。
しかし、植物は、防御網のほころびを監視する免疫受容体も持ち合わせています。これでは、進化が得意な病原菌も、簡単に攻撃の手を増やせません。これが、一定種類の受容体で身を守る秘訣のようです。
ここまで、病原菌から植物がどのように身を守るかを見てきましたが、実は、植物の内部には、普通に存在する「常在菌」が無数に生息しています。ヒトの腸内細菌と似たような状況です。
常在菌は一つ間違えれば病気を引き起こすことがありますが、病原菌へのバリアになり、環境の変化へのクッションとして働くと考えられています。植物の免疫受容体は常在菌が平穏に保たれているかも監視し、バランスを調整する役割がありそうです。