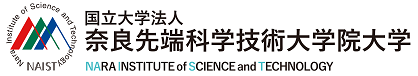~広報誌「せんたん」から~
[2014年1月号]
バイオサイエンス研究科 植物免疫学研究室 西條雄介准教授

2段階で防御
生物とせめぎ合いながら生活している。病気 を起こす悪玉の微生物が侵入すれば排除し、善玉は受け入れて共存共栄を図る。そんな動物の免疫システムに似た精妙な仕組みを備え ていることが明らかになってきた。
その背景には分子遺伝学に適した植物・微生物のモデル研究系の開発や分子生物学の研 究手段の飛躍的な発達がある。
西條准教授によると、これまでの知見から、 実にダイナミックな仕組みが提唱されている。 免疫反応の担い手になる植物体内のセンサー(受容体)は、体表や組織内に異物である微生物が入り込むと、まず微生物一般に特徴的な分子構造を認識して、「自分と異なる生物が 入って来た」と免疫の仕組みを活発にする。次の段階がユニークで、自己の細胞の状態を モニターする別のセンサーで「ダメージは受けていないか」「健常な生理状態を保ってい るか」と傷害の状況を判断し、有害であれば 防御反応を発動し排除するらしい。動物のように個別の異物に対応して抗体をつくる獲得 免疫はないが、植物免疫も工夫された巧妙なシステムだ。
「微生物によく保存された分子の構造、例 えば細菌で言うと、鞭毛のフラジェリンという タンパク質を植物のセンサーが認識することによって誘導される免疫システム。このバリアー のおかげで、ほとんどの微生物は植物に感染できない。しかしごく一部の微生物がこれを避けたり抑えたりして植物体内に棲息している。そんな微生物が植物細胞に働きかける仕組みから、実は植物についても多くのことが発見されていて、両者の駆引きに根差した分子生物 学は驚きの連続です」と西條准教授。作物に甚大な病害を引き起こす病原微生物を中心に研究してきた植物病理学などの流れとリンクするかたちで、包括的に、植物と環境中の微生 物の相互作用を解明するのが目的だ。
-

微生物成分のセンサー(受容体)と危険信号のセンサー(受容体)との機能的な連携にもとづく2段構えの植物免疫システム -

ペプチド性の危険信号因子(緑色蛍光で標識)が、障害 部位の周辺の細胞外スペースに蓄積される様子。このような仕組みで周囲の細胞へ警報が伝わり、植物組織 から個体全体の免疫力アップにつながると考えられる
基本原理を実証

西條研究室の具体的なテーマは、病原体の 侵入から免疫の発動までの間にどのような情 報伝達の機構があるか、詳しく探ること。植物の受容体は、微生物のタンパク質や自己の 細胞が壊れて出るタンパク質の断片(ペプチド)などの成分、ストレスがかかっている状 態を危険因子として感知しているとみられるが、それらの因子や受容体を突き止めることによって関連を明らかにする。
最近の大きな成果は、シロイヌナズナを材料にした分子遺伝学的な研究により、微生物(異物)を感知する受容体と植物細胞の破砕成分の受容体が、ともに細胞の膜に局在していて互いに連絡して協調したり、相補的に働いたりして、効率的に免疫を強めて稼働させていることを突き止めた。免疫システムの2段構え構造を実証したことになる。
西條准教授は「危険信号の認識に中心的な 役割を果たす遺伝子を知り、どのようにして植物の免疫に厚みをもたらしているのかが当面のテーマ」と説明する。
野外では、光・温度・湿度など環境条件が つねに変動する中で微生物と応対する。その際に植物が取る適応戦略を明らかにすることもテーマに掲げた。環境変動に応じて細胞の状態をモニターする危険信号センサーを植物 は免疫の調節にも役立てていると考えるからだ。「このようなシステムのおかげで、ダメージが起こるようなトラブルに見舞われても生 命活動が維持されるということが分かってきたわけで、そのシステムをうまく活用して、作物のストレス耐性を向上させるなど応用面でも貢献したい」と抱負を語る。耐病性や生長促進などの関連で産業界からも注目される植物体内に共棲する微生物(エンドファイト)についても「病原体も植物に共棲する微生物から進化してきた特殊な存在と見なせる わけで、生物の多様性をもたらす基本原理に迫る上でも格好の題材」と目を向ける。西條准教授は、武蔵野で過ごした少年時代から野遊びなどで生き物と親しんだ。京都大学に入学してから植物分子生物学のおもしろさに魅せられた。米国のエール大学を経てドイツのマックスプランク研究所に移り、植物免疫研究グループのリーダーを勤めて、昨年4月に本学に赴任した。
「遺伝子解析が格段に高度になった一方で 材料の植物を健康に育てるなど研究の基本は相変わらず同じです」というのが実感だ。学生には「一緒に楽しんで研究しよう」と気遣う。本学については「京都から長く海外に出ていて、今度は再び古都の奈良で研究できるの は幸せ。変わり者にも寛容で研究者同士の垣根が低く、新しいテーマにチャレンジしやす い気風がいい」と評価する。
趣味は、アウトドアや散策。家族思いで「3歳の息子がドイツ語を話し始めたところで帰国することになりよかった。父親はドイツ語が話せないというのが分かる前に」と笑った。